
231
周年ブランディングが得意なデザイン会社5選!
未来を動かす、周年ブランディング。
企業の節目をブランド強化の好機に変える、実績豊富な5社の特徴や強みを詳しくご紹介します。
周年ブランディングとは?
周年ブランディングとは、創業〇周年などの節目を単なる記念行事にとどめず、企業ブランドの価値向上や再構築につなげる戦略的施策です。過去を振り返り、未来のビジョンを明確に示す絶好の機会であり、その活かし方次第で社内の士気や社外の評価、ブランド価値が大きく変わります。本記事では、周年ブランディングの基本や効果、つまずきやすい課題、制作会社に依頼するメリット、パートナー選びのポイントを解説し、実績豊富な5社を厳選して紹介します。
周年事業が「ブランド資産」になる4つの機会

多くの企業が周年事業を単なる社内イベントや記念品制作で終わらせがちですが、戦略的に設計すれば、周年は長期的なブランド資産へと変わります。周年を通じて再定義した理念やビジョンは、その後の営業活動、採用、社内文化にまで波及し、持続的な企業価値向上の基盤となります。
【機会1】社内外に改めて企業理念を伝える
周年は、日々の業務の中では伝えきれない企業の理念やパーパスを、社員・顧客・取引先などあらゆるステークホルダーに改めて発信できる貴重な機会です。歴史や実績を振り返るだけでなく、「なぜこの事業を続けているのか」「どんな未来を目指しているのか」という存在意義を明確にすることで、社内の共感や社外からの信頼を強化できます。
【機会2】次世代への承継を図る
周年をきっかけに社史や理念を整理することは、単なる記録作業ではなく、次世代の経営層や社員にバトンを渡す重要なプロセスです。過去の挑戦や成功体験、そこに込められた価値観を体系的にまとめることで、新しい世代が企業の本質を理解し、未来の方向性を自分たちの言葉で語れるようになります。
【機会3】社員のモチベーションを高める
節目を共有する場は、組織に一体感と誇りをもたらします。周年を通じてこれまでの成果を讃え、社員一人ひとりの貢献を可視化することで、自己肯定感やチームとしての結束力が向上します。また「自分たちはこの歴史の一部であり、未来をつくる存在だ」という意識が芽生え、日々の業務へのモチベーション向上につながります。
【機会4】採用・広報・営業など各方面にブーストをかける
周年施策は社内イベントにとどまらず、社外発信の強力なコンテンツにもなります。メディア露出やSNSキャンペーンを通じて企業の魅力を広く発信することで、採用ブランド力を高め、共感を持つ人材の獲得につなげられます。また、営業活動においても、周年を契機に作成した動画やパンフレットが信頼構築の材料となり、商談のきっかけや関係強化のツールとして活用できます。
多くの企業が抱える周年事業の4つの課題

周年事業を成功させるには、単なる記念行事の枠を超え、企業の価値や存在意義を社内外に再確認させる仕掛けが欠かせません。しかし、現場では「何から始めればいいのか分からない」「盛り上がったのは当日だけ」といった課題に直面するケースが少なくありません。こうした失敗は、事前の戦略設計や巻き込みの工夫次第で防ぐことが可能です。次に、多くの企業が陥りやすい4つの典型的な課題をご紹介します。
【課題1】何をすべきか分からない
周年事業の企画段階で「そもそも何から始めれば良いのか」が明確にならず、結局これまでの慣習や前例に倣って形式的な社内式典だけで終わってしまうケースは少なくありません。本来、周年は企業の過去・現在・未来をつなぐ重要な節目ですが、目的やゴールを設定しないまま進めると、せっかくの機会を十分に活かせないまま形だけの行事に終わってしまいます。
【課題2】社外へのアピールができていない
周年施策が社内向けの祝賀や記念品配布などにとどまり、顧客や取引先、市場に向けた情報発信やブランディング強化につながっていないケースも多く見られます。周年をきっかけにした新たな発信やプロモーションを行わないと、外部にとっては単なる“社内のお祝い”にしか映らず、ブランド価値向上の機会を逃してしまいます。
【課題3】社内の共感を得られない
企画や方向性が経営層や一部の担当部署だけで決まり、現場の声や意見が反映されないまま進行してしまうと、社員が主体的に関わる意識を持てず、温度差が生じます。その結果、周年の意義やメッセージが十分に浸透せず、組織全体の一体感を高める機会が失われてしまいます。
【課題4】単発で終わっている
周年ロゴや記念誌の制作、記念イベントなど、一度きりの施策で終わってしまうケースも少なくありません。こうした単発施策は、その場では盛り上がっても、中長期的なブランド価値の蓄積や企業文化の醸成にはつながりにくいのが現実です。周年をブランド資産に変えるには、一貫性と継続性を持たせた計画が欠かせません。
周年ブランディング 代表的な8つの施策
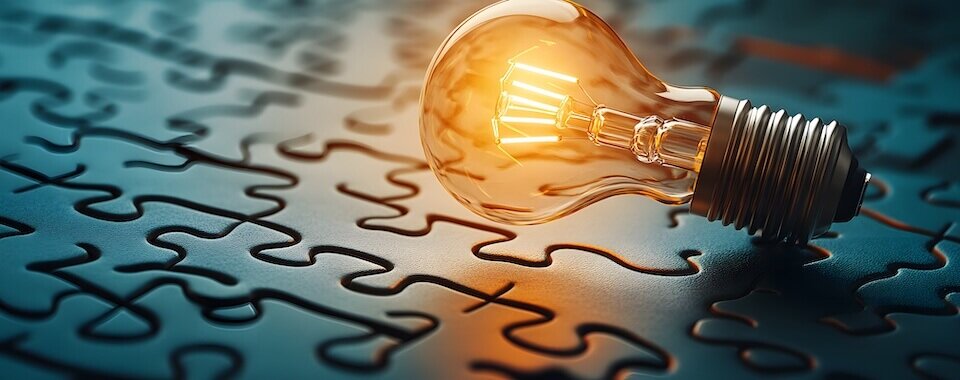
周年ブランディングを効果的に進めるには、単なる記念行事やデザイン制作にとどまらず、企業の歴史や理念、未来へのビジョンを多角的に発信するための施策を組み合わせることが重要です。象徴となるスローガンやロゴの開発から、映像・出版物・Webといった情報発信ツール、社員参加型の取り組みやイベント、さらにはSNSや広告を活用した広報展開まで、さまざまな手法を連動させることで、周年をブランド価値向上の大きな転機へと変えることができます。
【施策1】周年スローガンやコンセプトの開発
周年のテーマや方向性を象徴する言葉を開発し、全ての施策の中核として活用します。短く印象的なスローガンは、社員や顧客の心に強く残り、周年の意義を直感的に伝える強力なフックとなります。たとえば「挑戦の〇〇年」「未来へつなぐ〇〇」など、歴史と未来の両方を示すワードを設定することで、メッセージに一貫性と深みを持たせられます。完成したスローガンは、社内資料から広告、イベント演出まで幅広く展開でき、周年プロジェクト全体の統一感を生み出します。
【施策2】周年ロゴ開発
周年の象徴となるロゴは、記念のムードを視覚的に表現し、社内外の共通認識を高める役割を持ちます。単なる数字表記ではなく、スローガンや周年の世界観を反映させることで、ブランドストーリーを語るシンボルへと昇華します。完成したロゴは記念品や広告、Webサイト、SNS、イベント装飾など、あらゆる媒体で統一使用することで、周年のメッセージを繰り返し印象づける効果があります。また、後年の資料や社史にも残るため、企業の歴史を彩る重要なビジュアル資産となります。
【施策3】周年動画/ブランディング動画の制作
企業の歩みや価値観、これからの挑戦を映像で表現し、言葉だけでは伝えきれない感動や共感を引き出します。社員インタビューで社内の声を届けたり、過去の映像資料や写真を交えて歴史を描くドキュメンタリー形式にしたり、モーショングラフィックスで未来のビジョンをスタイリッシュに表現するなど、目的に応じた手法が選べます。動画は式典や社内イベントでの上映はもちろん、SNSやYouTubeで公開することで、顧客やパートナー企業にもメッセージを届けられます。周年の感動を最大化する、視覚と聴覚に訴えるコンテンツです。
【施策4】キービジュアルや周年サイトの制作
周年の世界観を象徴的に伝えるキービジュアルを開発し、ポスター、パンフレット、会場装飾、Webなどに一貫して展開します。特設の周年サイトでは、イベント情報やプロジェクト進捗、トップメッセージ、社員・顧客の声などを発信し、社内外の関心を高めます。オンラインならではの仕掛けとして、過去のアーカイブ公開や記念動画の配信、SNSキャンペーンとの連動も可能。周年の情報発信拠点として機能させることで、ブランドの一体感を強化します。
【施策5】周年記念誌/社史の制作
創業から現在に至るまでの歴史、理念、象徴的な出来事を体系的にまとめた記念誌や社史は、周年の集大成としての価値があります。単なる年表や記録にとどまらず、社員や経営陣、取引先のインタビューや秘話、写真資料などを盛り込むことで、読み物としての魅力が増します。後世に残す資料としての役割はもちろん、採用活動での配布や取引先への贈呈など広報ツールとしても活用可能。周年の重みとブランドの信頼感を、形ある冊子で伝えられます。
【施策6】記念イベント(リアル/オンライン)
周年の節目を祝う式典やパーティー、フォーラムなどを企画し、社員、顧客、パートナー企業との絆を深めます。リアル会場での華やかな演出や、遠隔地の参加者を巻き込むオンライン配信など、目的や参加層に応じた形態を選択可能です。社内向けには功労者表彰やチーム表彰、社外向けには新商品発表や感謝イベントを組み込み、感謝と未来への決意を共有する場とします。周年の感動を参加者全員で共有できる重要な機会です。
【施策7】社員インタビューや社内プロジェクト
周年を単なる会社の行事ではなく、社員一人ひとりの「自分ごと」として感じてもらうために、社員の声やストーリーを集めて発信します。Webや社内報、動画コンテンツで共有することで、組織内の相互理解や一体感が高まります。また、部署横断の社内プロジェクトを立ち上げ、周年施策に社員自らが関わる仕組みを作ると、主体性とモチベーションが向上。周年を機に社内文化をさらに育むことができます。
【施策8】SNSや広告を活用したプロモーション
周年を契機にブランドの認知や好感度を高めるため、SNS投稿やWeb広告、プレスリリース、メディア露出を計画的に実施します。周年ロゴやスローガンを活用したキャンペーンやハッシュタグ企画でオンライン上の拡散力を高め、同時に屋外広告や雑誌掲載などオフライン施策と連動させることで、より幅広い層へのリーチが可能になります。情報発信を一過性で終わらせず、周年期間を通じて継続的に話題を生み出すことが、効果を最大化するポイントです。
周年事業をブランディング会社に依頼する3つのメリット
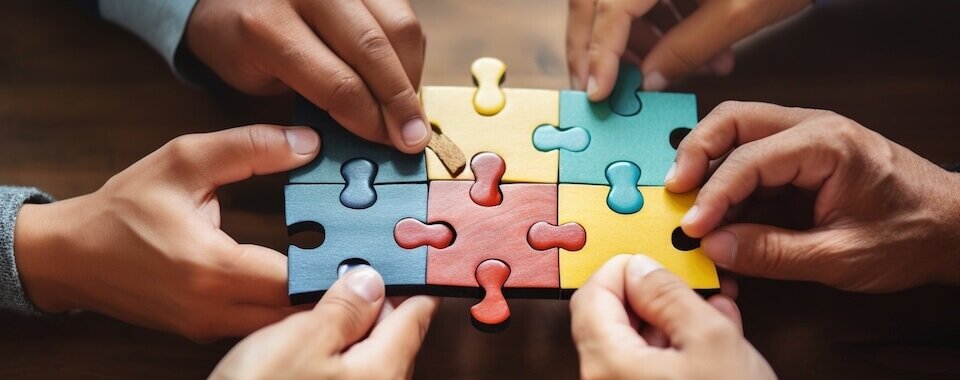
周年は、単なる記念イベントではなく、企業の歴史と未来をつなぐ大きな節目です。しかし、社内だけで企画・制作・運営までを担うには、時間・人員・専門性のすべてが求められ、現実的に負担が大きくなります。そこで有効なのが、ブランディング会社との協業です。単なる外注先ではなく、企業のパートナーとして共に歩むことで、次のようなメリットが得られます。
【メリット1】一貫したクリエイティブ制作
周年ブランディングでは、ロゴや映像、記念誌、Webサイト、広告など、多岐にわたるクリエイティブ制作が発生します。外部のブランディング会社に一括して依頼すれば、すべての媒体で統一された世界観・トーン&マナーを維持できます。また、デザインやメッセージからブランドの印象を強固にし、社内外に「一貫性のある姿勢」を示すことができます。結果として、ブランドへの信頼感と好感度が高まり、周年の成果を長期的な資産として残すことができます。
【メリット2】戦略とクリエイティブを結びつける提案
ブランディング会社は、単に見栄えの良い制作物を作るだけではなく、企業理念や中長期的なビジョンを踏まえた戦略的なアプローチを提案します。そして、企画立案からコンテンツ開発、デザイン、プロモーションまでをワンストップで行うことで、メッセージや世界観が施策全体に貫かれます。これにより、周年プロジェクトが「その場限りのイベント」ではなく、企業の未来を切り開くきっかけとして機能するようになります。
【メリット3】担当者の負担軽減
周年事業は、通常業務と並行して進行することが多く、担当者への負荷が非常に大きくなります。部門間調整や進行管理、制作物の監修など、多岐にわたる業務をすべて自社内で対応するのは現実的に困難です。一方、ブランディング会社に依頼すれば、プロジェクト全体のディレクションやスケジュール管理を任せられるため、社内担当者は意思決定や社内浸透などのコア業務に集中できます。これにより、社内のリソースを効率的に活用しながら、クオリティとスピードを両立できます。
制作会社選び 5つのチェックポイント

周年という節目は、これまでの歴史を振り返るだけでなく、これからの未来に向けた物語を描く絶好のチャンスです。そのストーリーをどう形にするかで、周年事業の成果は大きく変わります。だからこそ、制作会社を選ぶ際には「誰と組むか」が重要です。以下の5つの観点から、自社に寄り添い、共にゴールを目指せる最適なパートナーを見極めましょう。
【チェック1】得意な領域(デザイン/映像/編集など)
制作会社ごとに強みは異なります。たとえば、映像表現に長けた会社はダイナミックな周年動画を得意とし、編集系の会社は質の高い記念誌や社史を生み出します。Webやグラフィックデザインに特化した会社なら、キービジュアルや特設サイトでブランド世界観を魅力的に発信できます。自社が「何を最も重視するのか」を明確にし、その分野で確かな実績を持つ会社を選ぶことが成功への第一歩です。
【チェック2】理念や経営戦略との連動
周年事業は単なる制作物づくりではありません。企業のパーパスやビジョンを深く理解し、経営戦略と連動させた提案ができるかが重要です。制作の過程で企業の存在意義や方向性を改めて整理し、それを表現に落とし込める会社であれば、単発ではなく未来へつながる成果を生み出すことができます。
【チェック3】社内巻き込みのノウハウ
周年事業を社内浸透させるには、社員が「自分ごと」として関われる仕組みづくりが不可欠です。ワークショップや社員インタビューなど、インナーブランディングの手法を駆使して社員の声や想いを引き出せる会社は、自然と社内の熱量を高め、周年事業を成功へと導くことができます。
【チェック4】担当者との相性
周年事業は数カ月から1年以上にわたる長期プロジェクトになることも少なくありません。だからこそ、担当者とのコミュニケーションのしやすさや価値観の一致は、成果に直結します。丁寧にヒアリングし、課題や状況を的確に把握したうえで伴走してくれるパートナーを選びましょう。
【チェック5】公開されている実績の深さ
実績の豊富さは一つの目安ですが、見た目の完成度だけでは判断できません。どんな課題を抱えたクライアントに対して、どのような戦略やプロセスで解決に導いたのかまでを開示している会社は信頼度が高いといえます。事例の背景や成果まで把握できれば、自社の課題解決に本当にマッチするかを判断しやすくなります。
周年ブランディングが得意なデザイン会社5選

企業にとって周年は、単なる節目ではなく、ブランドを再定義し、未来へのビジョンを社内外に発信する絶好の機会です。その成功のカギを握るのが、パートナーとなる制作会社の選定。周年ロゴや映像制作、記念誌編集からイベント運営まで、必要な領域は多岐にわたり、戦略とクリエイティブを一体化できる実力が求められます。
ここでは、豊富な実績と高い専門性を持ち、周年事業をブランド価値向上のチャンスへと導くデザイン会社5社を厳選してご紹介します。各社の特徴や得意分野、主な実績を比較しながら、自社に最適なパートナー選びの参考にしてください。
パドルデザインカンパニーは、周年ロゴ・記念サイト・動画・記念誌・グッズなど周年記念事業に関わる企画・制作を一気通貫で幅広く対応するブランディング会社です。ブランディングディレクター、コピーライター、アートディレクター、映像ディレクターなど多様なクリエイターがチームを編成し、企業の歴史と未来を融合させた“周年ブランディング”を推進。特に製造業での実績が豊富で、周年をブランド強化の機会と捉える企業に信頼されています。
《事業内容》
・周年ロゴ・タグライン開発、ブランド戦略設計
・周年サイト・周年動画・記念誌制作
・記念品・ノベルティ・グッズ制作支援
・周年イベント企画・実施支援
《周年ブランディング実績の一例》
鎌ケ谷巧業株式会社
シモダL&C株式会社
ポーライト株式会社
新光ネームプレート株式会社
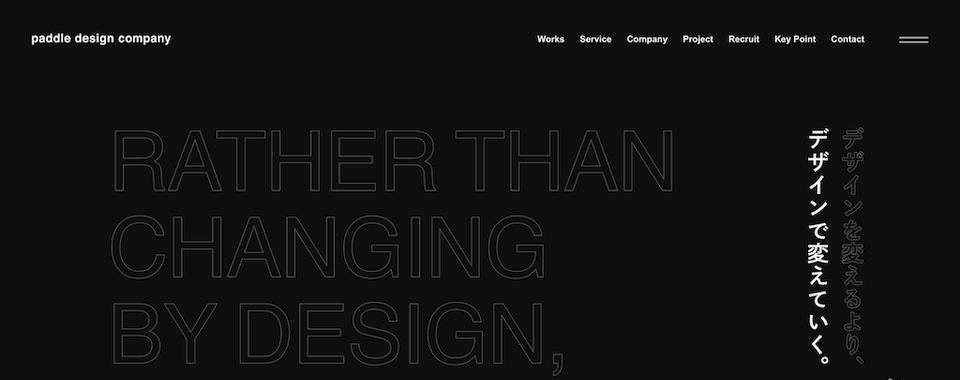
2.株式会社チビコ
株式会社チビコは、「経営としてのデザイン」を理念に、企業の理念やビジョンを的確に可視化し、戦略立案からCI/VI開発、Web・広告・パッケージなどのデザイン制作、プロモーション展開までを一貫して手がけることで、業界や規模を問わず多くの企業のブランド価値向上と長期的な信頼構築を支援するブランディングの専門会社です。
《事業内容》
・ブランド戦略立案、コンセプト・CI/VI設計
・市場・競合リサーチ、分析、レポート作成
・各種デザイン制作(Web、広告、カタログ、パッケージ、空間など)
・プロダクト開発、パッケージデザイン、空間デザイン

3.アドバンド株式会社
アドバンド株式会社は、社史・記念誌編集とデジタル展開を融合した周年支援を得意とする編集制作企業です。歴史的背景や世の中の流れを踏まえつつ、読み手が引き込まれるドラマティックな物語を設計。周年記念誌だけでなく、Webサイトや動画まで含めたマルチメディアで表現可能。対象読者や用途別に最適な媒体と構成を提案し、“会社の歴史”をブランド力に変えるコンテンツ制作に強みがあります。
《事業内容》
・社史・記念誌の編集・制作/取材・原稿執筆
・周年サイトや周年記念動画などのデジタル媒体制作
・ターゲットや用途に応じた媒体提案・構成設計
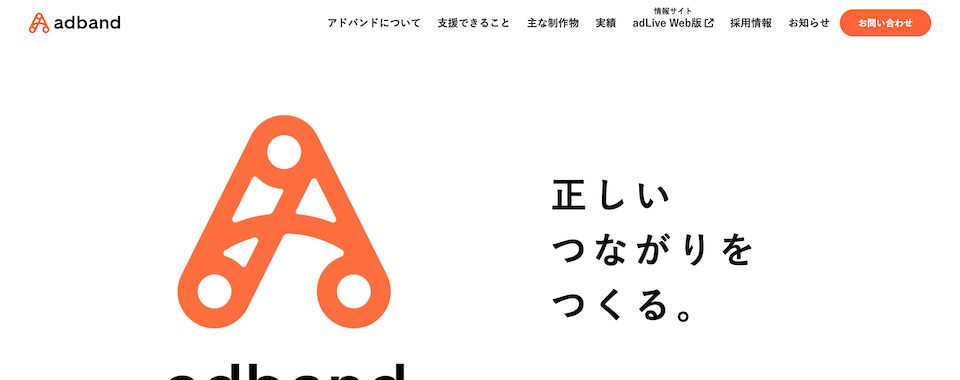
4.株式会社映像制作センター
株式会社映像制作センターは、NHKドキュメンタリー出身スタッフによる「脚本と取材重視の周年映像」が強み。官公庁や大手企業の創立記念映像制作を多数手掛け、3D CGや5Kドローン映像など先端技術も活用可能。再編集による他用途転用も対応できる柔軟性を持ち、歴史と未来を織り交ぜた映像表現で、周年事業をドラマチックに彩ります。大規模で質の高い映像制作を求める企業におすすめです。
《事業内容》
周年記念/社史映像の企画・脚本・撮影・編集
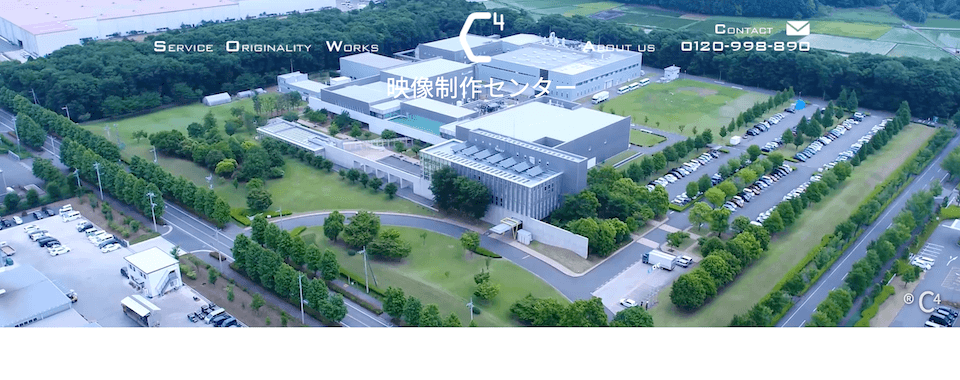
5.株式会社日立ドキュメントソリューションズ
日立ドキュメントソリューションズは、周年記念事業を“社内モチベーション向上 × ブランド機会”と捉え、映像・サイト・記念誌・ノベルティ・式典運営まで包括的にプロデュース可能な総合支援企業です。長年の企業支援実績を活かし、式典や広告、周年ロゴ策定、記念品開発など多面的にカバー。特に規模の大きい周年事業や式典形式の施策に強みがあります。
《事業内容》
・周年記念プロジェクト総合プロデュース(映像・式典・広告など)
・周年ロゴ・タグライン策定、記念品・ノベルティ制作
・社史/周年誌、Webサイト、広告制作、式典運営サポート
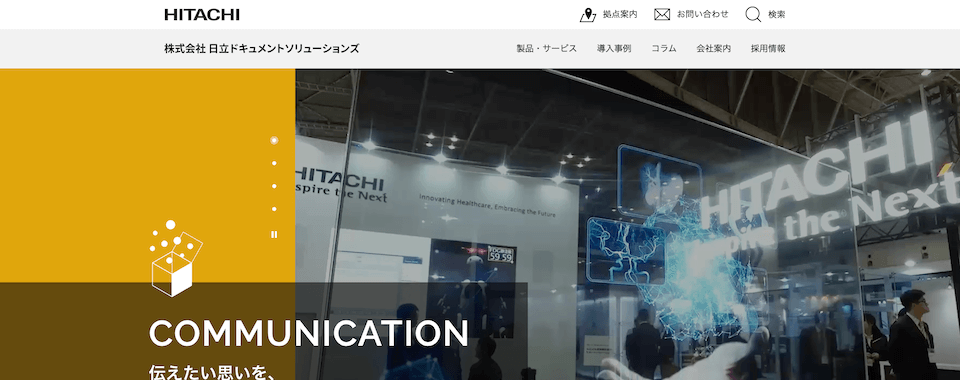
周年ブランディングのよくある質問

周年ブランディングは企業にとって、過去を振り返り未来を描く絶好の機会です。しかし、実際に取り組もうとすると「何周年からやるべき?」「準備はいつから?」「予算はどれくらい?」など、多くの疑問が生まれます。ここでは、周年事業を検討・実施する際によく寄せられる質問と、その具体的な回答をまとめました。初めての周年プロジェクトにも、既に経験がある企業にも役立つ実践的なヒントをお届けします。
Q1. 周年ブランディングは何周年から行うべきですか?
節目としては「10周年」「20周年」「30周年」が多いですが、5周年や13周年など中間の年でも実施されます。重要なのは“何周年か”よりも、そのタイミングで何を伝えたいか、どのような効果を狙うかという目的設定です。
Q2.どのくらい前から準備すればいいですか?
最低でも1年前、可能であれば1年半前からの準備が理想です。コンセプト策定や社内調整、制作スケジュールの確保、外部パートナー選定などに時間がかかるため、余裕を持った計画が成功のポイントとなります。
Q3.予算はどのくらい必要ですか?
施策内容によって大きく変動します。周年ロゴと動画制作のみなら数百万円規模、記念誌やイベント、Web特設サイトまで含めると1,000万円以上かかるケースもあります。まずは目的に応じた必須施策を整理し、優先順位をつけて見積もりをご依頼ください。
Q4.周年事業は社内向けと社外向け、どちらに重点を置くべきですか?
双方をバランスよく設計するのが理想です。社内向けでは理念浸透やモチベーション向上を、社外向けではブランド価値や信頼性の向上を狙います。同じメッセージを社内外に伝えることで、一貫性ある周年ブランディングが可能になります。
Q5.成果はどう測定しますか?
社外向けはWebアクセス数やSNS反応、メディア露出などの指標、社内向けは社員アンケートやイベント参加率、エンゲージメント調査などで定量・定性の両面から効果を把握します。
Q6.周年事業後に活用できるものはありますか?
ロゴやスローガン、映像、記念誌などは周年後も採用活動や営業資料、Webコンテンツとして再利用できます。単発で終わらせず、中長期的な資産として活用する設計が重要です。
周年ブランディング 5つの事前準備

周年ブランディングを成功させるためには、制作会社や社内プロジェクトチームとの打ち合わせに入る前に、以下のポイントを整理しておくことが重要です。事前準備が整っているほど、企画の精度が上がり、無駄な工数やコストを抑えることができます。
【準備1】周年ブランディングの目的を明確にする
周年事業を行う上で最も重要なのは、その目的を明確に定めることです。社員の士気向上、顧客や取引先への感謝の伝達、採用活動の強化、ブランド価値の再定義など、何を達成したいのかをはっきりさせることで、施策全体の方向性がぶれず、効果的なプロジェクト設計が可能になります。
【準備2】現在の課題を整理する
周年は、企業の課題解決にもつながる絶好の機会です。社員の理念理解不足、ブランドイメージの低下、情報発信力の弱さなど、現状の課題を洗い出しておくことで、周年施策を単なる記念行事ではなく、課題解決型の戦略として設計できます。
【準備3】予算とスケジュールの概算を立てる
周年事業は企画から実施まで長期にわたるため、事前に予算とスケジュールの目安を設定しておくことが重要です。優先度の高い施策と必須施策を整理し、理想的には1年以上前から準備を始めることで、余裕を持った進行と高品質な制作が可能になります。
【準備4】社内のキーパーソンと体制を確認する
周年事業は複数部署をまたぐため、関係者の調整が不可欠です。経営層や部門責任者、実務担当者など、意思決定や情報共有に関わるキーパーソンを早めに特定し、決裁フローや役割分担を明確化しておくことで、スムーズなプロジェクト運営が実現します。
【準備5】発信テーマやストーリーの方向性を考える
周年で伝えるべきメッセージやストーリーの骨格を事前に固めておくことで、制作のブレを防ぐことができます。過去の歴史や沿革を軸にするのか、未来ビジョンを前面に打ち出すのか、社員や顧客の声を中心に構成するのかなど、発信の核を明確にすることで、コンテンツの一貫性と訴求力が高まります。
まとめ|周年ブランディングは“未来への投資”である
周年ブランディングは、過去を振り返るだけでなく、未来へのビジョンを社内外に共有し、ブランド価値を高める大きなチャンスです。課題の整理、ブランドの再定義、未来への共感づくりを意識し、信頼できるパートナーと共に取り組むことで、節目を企業成長の起点に変えることができます。 「何から始めればいいか分からない…」そんな方こそ、まずは気になる制作会社に相談し、10年後、20年後に振り返って「やってよかった」と思える周年ブランディングを実現しましょう。
東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治





