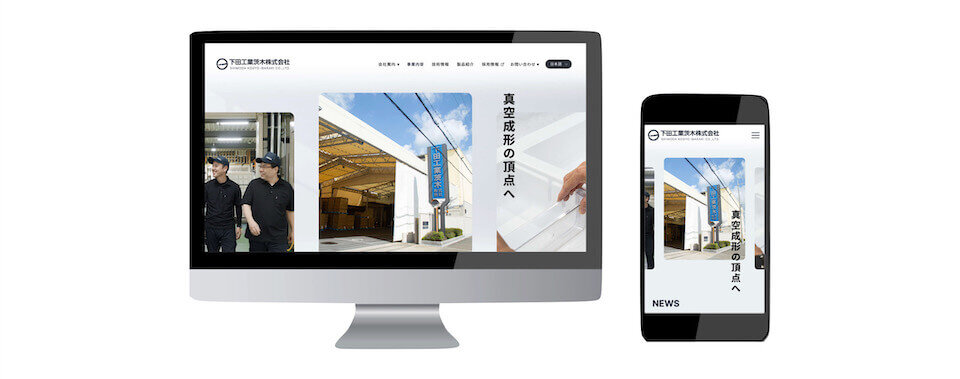228
企業の節目を変わり目に!周年を契機とした企業ブランディングの最前線
変わる勇気を、周年から。
変革・共創・発信を叶える、次世代の周年プロジェクト設計を解説します。
はじめに|なぜ今、周年に“変化”が求められるのか
かつて企業の周年といえば、式典や記念品の配布、社史の編纂といった「過去を祝う場」が中心でした。しかし近年、その在り方は大きく変わりつつあります。
働き方の変化、顧客価値観の多様化、社会課題との向き合いが企業に求められるなか、周年は“過去を称える場”から“未来に踏み出す機会”へと進化しています。
社員や社会は、単なる祝賀よりも「この企業は次に何を目指すのか」「どんな姿勢で未来を描いているのか」に関心を持っています。
つまり、今の周年には“変わらない価値”を示すだけでなく、“これからの変化”をどう表現するかが問われています。

未来に踏み出す機会とは?
周年は、企業にとって単なる節目ではなく、これまでの歴史や信頼を土台に“これからどう在るべきか”を社内外に示すチャンスです。
新たな経営ビジョンの策定、組織文化の見直し、ブランドの再定義。それらは普段の業務の延長ではなかなか着手できません。
だからこそ周年を、「過去を振り返る」だけでなく、「未来への第一歩を踏み出す起点」として活かすことで、変革の流れを自然に社内に浸透させることができます。周年は、企業が“変わりたい”と本気で言える、数少ない公的なタイミングなのです。
これからの変化とは?
企業を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。
デジタル化、脱炭素社会、価値観の多様化、そして人材の流動性。これまでの延長線上では通用しない時代に、企業も「あり方」そのものを問い直す必要があります。
このような変化のなかで求められるのは、「理念を軸に、どう変化するか」を明確にし、社内外に誠実に伝えていくことです。
つまり、“これからの変化”とは、ただの時代対応ではなく、企業のアイデンティティを再定義し、それを自らの言葉で発信する姿勢なのです。
時代は変わった。企業を取り巻く「5つの変化」

企業の周年を取り巻く環境は、過去とは比べものにならないほど複雑かつ多様化しています。これまでのように「歴史を振り返り、実績を称える」だけの周年では、ステークホルダーの心を動かすことは難しくなっています。
今、企業には“変わり続ける社会と、どう向き合い、未来を語るか”という姿勢が問われています。周年はその意思を伝える好機であり、経営の“今”と“これから”を示すブランド戦略の場に進化しつつあります。
ここでは、企業を取り巻く外部環境の「5つの変化」に注目し、なぜ周年の設計が見直されているのか、その背景を紐解きます。
【変化1】社会の価値観の転換(SDGs・ESG・多様性など)
企業はもはや「売上や規模」だけで評価される時代ではありません。
環境問題、社会課題への取り組み、組織の多様性など、どのような価値観で社会と関わっているかが、企業ブランドの根幹に関わる時代です。
周年も、「感謝」や「歴史」だけでなく、社会にどう貢献していくかの意思表明の場として進化が求められています。
【変化2】働き手の意識変化(キャリアの自己実現、企業理念への共感重視)
社員は報酬や安定だけでは動きません。
「この会社の理念に共感できるか」「社会とどうつながっているか」といった“働く意味”への問いが重視されるようになっています。
周年を通じて、理念やビジョンを再確認し、社員と共有する仕組みは、エンゲージメントを高める絶好の機会です。
【変化3】テクノロジー進化による情報発信の加速
SNSや動画配信、オンラインイベント、メタバースなど、企業の情報発信は一方通行ではなくなり、リアルタイムで評価・反応が返ってくる時代に突入しています。
周年においても、Web特設サイトやストーリービデオ、SNS展開など、共感を生むコンテンツ発信力が求められるようになっています。
【変化4】若年層を中心としたブランドへの“共感”志向
Z世代をはじめとする若年層は、「何をしているか」よりも「なぜそれをしているか」に敏感です。故に、企業の背景や哲学、ストーリーが透明であることが、ブランドへの好意形成や選択の基準になっています。
周年は、自社の“想い”や“歩み”を語る好機。共感を呼ぶブランド体験として再設計することが重要です。
【変化5】ステークホルダーとの関係性重視(取引先・地域・投資家)
企業活動は社内だけで完結せず、取引先や地域社会、株主・投資家との信頼構築がますます重要になっています。それに対し周年は、これら多様なステークホルダーに対して、「これからも一緒に進んでいきたい」という意思を発信できる場です。
共創型イベントやメッセージ発信を通じて、関係性を再強化する機会として活用できます。
「祝う」から「進める」へ。共感と未来を生む、今どきの周年プロジェクト設計

周年は、企業がこれまで積み重ねてきた信頼や実績を振り返る場であると同時に、これからの進むべき方向を社内外に示す“未来への意思表明”の機会でもあります。
かつてのような一方的な祝賀行事にとどまらず、今の時代に求められているのは、「共感」や「参加」を軸にした、双方向の周年プロジェクトです。
では、企業がこの変化にどう応えるべきか。ここでは、今どきの周年プロジェクトを成功に導くための3つの設計ポイントをご紹介します。
【Point1】「意味ある参加」への期待
社員はもはや“観客”ではなく、自分たちの声や想いが反映される「共創者」として関わりたいと考えています。インタビューや動画出演、企画公募など、一人ひとりが“自分ごと化”できる参加設計が、当事者意識とブランドへの共感を生み出します。
【Point2】共感できるブランドへの進化
ブランドの歩みや成果を示すだけでなく、共感できる価値観やストーリー性があるかどうかが問われています。社員の声や創業の想いなど、“人”に焦点を当てたストーリーテリング型コンテンツが、信頼と親しみを伴ったブランド発信へとつながります。
【Point3】透明性と一貫性のある発信
今の社会では、言葉と行動が一致しているかどうかがブランドの信頼に直結します。CSRや採用、地域との連携など、実際の活動と周年のメッセージが結びつくことで、「見せかけではない姿勢」として社内外に伝わります。
周年の在り方はここまで変わった|今どきの周年プロジェクト動向

これまで「周年=感謝やお祝いの場」という固定観念がありましたが、今その役割が大きく変わりつつあります。
現代の周年は、企業が抱える課題を見つめ直し、ブランドや理念を再定義する“変革のチャンス”として設計されるケースが増えています。
さらに、デジタル技術の進化や社員との共創ニーズの高まりにより、その手法やアウトプットもかつてとは一線を画しています。
ここでは、企業の周年プロジェクトがどのように進化しているのか、最新のトレンドとともにご紹介します。
昔ながらの「感謝イベント」から「経営課題解決型周年」へ
かつての周年といえば、式典や記念パーティー、社史の発行など、社内外への“感謝”を示すことが主目的でした。
しかし近年では、周年を単なる祝賀行事にとどめず、経営課題の解決やブランド再構築、理念の再浸透など、未来志向の戦略的プロジェクトとして捉える企業が急増。「過去の総括」ではなく「未来の起点」として周年を設計する動きが、急速に加速しています。
各業界で進む「周年のDX化」(メタバース社史・動画AI・SNS拡張)
デジタル技術の進化により、周年の表現方法も大きく変化しています。
メタバース上に構築されたバーチャル社史空間、AI生成の周年動画、SNSを活用した記念企画の拡散など、参加体験型・双方向型の周年コンテンツが目立つようになりました。物理的なイベントや印刷物だけでなく、デジタルならではの“拡張された記憶と共感”の設計が求められていると言えます。
社員と共創するブランド開発:社員ワークショップや社内公募の活用
企業の未来を描く周年プロジェクトにおいて、社員はもはや受け手ではなく“共創者”です。
理念やタグラインの再定義、周年ロゴやコンセプト動画制作などに、ワークショップ形式で社員の声を取り入れたり、社内公募でアイデアを集めたりする手法が広がっています。
これにより、企業のメッセージが“自分ごと化”され、組織全体の一体感やエンゲージメントが自然と高まっていきます。
周年を通じて“社会とつながる”
近年、B2B企業においても「周年=社内イベント」という枠を超え、地域・社会とのつながりを深める“社会共創型周年”へとシフトする動きが加速しています。
単なる企業の自己完結ではなく、地域との連携や、ESG・SDGsと連動した取り組みを通じて、「社会にどう価値を還元するか」を明確に伝える周年プロジェクトが注目を集めています。
例えば、地域の学校や団体との協業、地元クリエイターとのアートプロジェクト、パブリックスペースでの展示やイベント開催など、周年を軸にした“共創の場づくり”がその一例です。
こうした取り組みは、社会との接点を広げるだけでなく、企業の姿勢や価値観を広く共有するブランド発信のチャンスにもなります。
周年を「社会との対話の場」として捉えることで、企業は単なる記念年を超えた、持続可能な価値共創の起点を生み出すことができるのです。
「記録」から「資産」へ|周年コンテンツの継続戦略

周年プロジェクトで生まれた動画・特設サイト・ロゴなどのコンテンツは、イベントが終わっても価値を持ち続けます。
従来は「記録物」として保管されるだけだったものを、今はブランド資産として中長期的に活用する戦略が重要視されています。
周年後も活きる設計を意識することで、投資対効果が高く、持続可能なブランディングが実現できます。
周年動画/周年特設サイト/周年ロゴの再活用事例
制作した周年コンテンツは、企業紹介・営業資料・採用PRなどへの転用が可能です。
例えば、周年動画は会社説明会や展示会でのプレゼン素材に、周年サイトはコーポレートサイトの信頼性向上に貢献。周年ロゴは名刺・封筒・製品パッケージに応用されるなど、ブランドアイデンティティの一貫性を支える素材として再活用されるケースが増えています。
採用・IR・営業に活きる“周年コンテンツのリサイクル”
周年で生まれたストーリーやビジュアルは、企業の「らしさ」や「信頼感」を伝える強力な武器になります。
採用活動では、企業理念や社風を伝える素材として活用でき、IRでは経営の持続性やビジョンを語る資料に。営業の現場でも、過去からの積み重ねや未来志向を伝えるツールとして効果的です。周年コンテンツの“リサイクル”は、伝える力を高める再投資となります。
社内アーカイブとナレッジ共有の新しい形
周年の過程で得られたノウハウや資料をデジタルアーカイブ化することで、全社でのナレッジ共有や後進への教育資源としても活用できます。
特に、周年企画に関わった社員の声やプロジェクトプロセスの記録は、今後の社内イベントや経営課題に向き合う際の貴重なヒントとなります。周年は“記録”で終わらせず、組織に知見を蓄積し、未来に継承する体制づくりが重要です。
周年が企業変革に火をつけた|シモダL&C株式会社
下田グループ4社の統合から4年、100周年を機に新社名・MVV・ロゴを策定し、ブランド変革を3カ年で実施。「つなぎ、つくり、こたえる。」を旗印に、次の100年を見据えた新たな一歩を踏み出しました。
周年動画|新社名発表、新たなる門出。
100周年の集大成として制作された周年動画では、新社名「シモダL&C株式会社」を発表。600名の社員に向けてMVVとロゴに込めた想いを伝える、ブランド刷新の象徴となる映像です。
社名変更|下田工業からシモダL&Cへ
100周年を機に、社名を「シモダL&C株式会社」へ変更。「Link」と「Create」を取り入れた新社名に、企業理念「企業は永遠なり」と顧客の信頼を継承する想いが込められています。
周年サイト|思いを一つに
「Growing together.」をテーマに、社員参加型のインタビューやトークセッションを展開。お客様・社員との共創と成長の軌跡を、アニメーションで魅せる特設サイトに集約しました。
イベントオープニング動画|イベントへの期待感を醸成
600名以上が参加した周年イベントの冒頭で上映されたオープニングムービー。新スローガン・ロゴ・100年の歩みを映像で表現し、これからの飛躍を印象付けました。
MVV開発|つなぎ、つくり、こたえる。
新ブランドの核となるMVVを策定。「挑む企業をつなぎ、革新をつくる。」というミッションを軸に、100年企業のこれからを社員・社会と共有する価値基盤を構築しました。
ブランディング動画|新ブランドとしての決意を新たに。
新社名発表後に公開されたブランディング動画 第二弾。リレー形式の演出で「決意」をテーマに、次の100年への意志を社員の想いと共に映し出します。
コーポレートサイト|コンセプトをより直感的に
ブランド動画をファーストビューに配置し、世界観を直感的に伝えるコーポレートサイトへ刷新。スローガン「つなぎ、つくり、こたえる。」をトップに掲げ、紫紺を基調にブランドの統一感を演出。事業内容は商材・納入分野を整理し、ユーザーが全体像を把握しやすい構成にしました。
会社案内パンフレット|更新性を備えた営業ツールに
会社案内を紙からPowerPointに刷新し、更新性と柔軟性を強化。ブランドコンセプトから事業内容、CSRや沿革まで網羅し、営業・採用・IRで活用できる実践的ツールを整備しました。
グループ企業のWebサイトも|下田工業茨城株式会社
100周年を機に、下田工業茨木株式会社のコーポレートサイトを刷新。写真・動画撮影を並行して行い、技術力が伝わる高品質なビジュアル素材を開発しました。縦横スクロールを織り交ぜた動的デザインにより、親しみやすく優しい印象を演出。グレー背景に角丸画像を配し、企業の魅力を直感的に伝える構成としています。
これからの周年に求められる3つの視点

企業の周年は、単なる節目を祝う行事から、これからの経営の方向性を示す「意思の発信」に変わりつつあります。変化の激しい時代において、周年は“過去のまとめ”ではなく、“未来を切り拓く設計図”として捉え直す必要があります。では、そのために企業が持つべき視点とは何か。本項では、これからの周年設計において欠かせない3つの視点を紹介します。
変化への挑戦|リスク回避でなく、意思表示の機会に
企業の周年は、変化を避けるための“守り”の場ではなく、変化を歓迎し自ら意思を表明する“攻め”の場へと進化しています。過去にとらわれず、時代に適応した新たな価値観や方針を堂々と発信することで、社会や社員に対する信頼と期待を獲得する重要なターニングポイントになります。
共創型アプローチ|社員・社会との“対話”を設計
周年を自社だけのイベントにせず、社員・地域・顧客・取引先など多様なステークホルダーと「共に考え、共に語る場」として設計することが求められています。トップダウンの発信から脱却し、双方向の“対話型”周年に転換することで、持続可能で共感されるブランドの土台が築かれます。
記念日後を見据えた設計|周年の“翌日”からブランド価値を育てる
周年は“その日限りのイベント”ではありません。プロジェクト終了後も活用できるロゴやメッセージ、ナレッジ資産の活用設計こそが、企業価値を長期にわたって育てる未来の種になります。大切なのは、周年後の1年・3年・5年を見据えて、ブランド資産をどう育て、どう循環させていくかという視点です。
おわりに|変わり目にしかできない、ブランドの進化を
周年は、過去を称えるだけでなく、“今こそ変われる”タイミング。理念やブランドを見直し、社会に新たな価値を示す好機です。次の節目を「記念日」で終わらせず、「変わり目」に変える準備を始めてください。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
《周年事業に関する記事一覧》
企業の節目を変わり目に!周年を契機とした企業ブランディングの最前線
周年は経営の転換点|ブランド再構築に活かす戦略的アプローチ
周年事業を成功に導く"インナーブランディング"の力
周年を機にMVV(ミッション/ビジョン/バリュー)を再浸透させる方法
周年ロゴとは?企業の節目を象徴するデザインとその役割
周年ロゴ制作の費用相場と制作期間|直依頼・代理店経由の違い
効果的な周年ツールとは?成功事例から紐解く5つのツール
成功する周年企画・ツール制作事例集
企業価値を高める周年ツール制作と費用プラン
周年ブランディングが得意なデザイン会社5選!
周年サイトで企業価値を高める!成功する構成とデザインを徹底解説
周年サイトに入れるべき10の必須コンテンツ
周年サイト制作の事前準備 完全ガイド
周年誌を外注する前に知っておきたい5つの基本
読まれる周年記念誌 完全ガイド|成果を出す構成・デザインのポイント
周年誌の企画アイデア集|"あゆみ"を感動に変える編集テーマ10選
周年記念誌のデザイン事例集|ブランドを象徴するビジュアル表現
周年動画とは?周年動画を制作する目的・メリット・成功事例を解説
社員参加型 周年動画の成功事例|社員主体でつくるブランディング動画
周年動画の制作方法|成功する企業アニバーサリームービーの作り方
企業向け周年動画 活用ガイド|目的別にわかる活用方法
周年オープニング動画の成功事例|感動と期待を生む構成ポイント
周年動画の制作費を徹底解説|企業規模別・用途別の費用相場
周年アイデア完全ガイド|周年事業・周年イベント企画の全手法
周年プロジェクト完全ガイド|進め方・事例・ツール制作まで徹底解説
周年事業を成功へと導くチェックリスト18項目