
19
ブランディングを加速させる「経営者の決意」と「担当者の情熱」
想いを「仕組み」に変えるとき、ブランドは文化になる。
経営者の理念と担当者の情熱を、日常の行動へ。必要なのは、“共感”と“実践”を循環させる仕組みづくりです。
決意と熱意をつなぐ仕組みづくり
ブランドが持続的に成長するためには、トップの決意と現場の情熱を“つなぐ回路”が必要です。どれほど素晴らしい理念を掲げても、共有と実践の仕組みがなければ、時間とともに風化してしまいます。
ここで重要になるのが、MVV(Mission/Vision/Value)開発からクレド開発までを一貫して整える“理念設計”のステップです。

MVV開発からクレド開発へ
MVVは企業の「存在理由・目指す未来・行動の価値観」を明文化したブランドの基盤です。しかし、掲げるだけでは意味がありません。日常の判断や行動にまで浸透させるためには、社員一人ひとりが“自分の言葉”として語れる状態をつくることが大切です。
その架け橋となるのがクレド(信条)です。クレドはMVVを日常行動に翻訳した「現場の羅針盤」。例えば、「お客様の期待を超える」を「お客様の声を一度で完結させる」と具体化するなど、誰もが日常業務で“どう動けば理念を体現できるか”を理解できる形に落とし込むことが大切です。
MVVを共有する社内研修・理念浸透活動の重要性
理念は共有されて初めて、文化になります。経営者が発信し、管理職が語り、社員が自らの体験として語れるようにするためには、ワークショップや社内研修など“対話型”の場づくりが欠かせません。
理念は、教えるのではなく、一緒に考える。このプロセスを通して、理念は「経営者の言葉」から「全員の実感」へと変わります。
さらに、社内報やイントラブログなどの発信を通じて理念を日常的に可視化し、小さな実践事例を称えることで、理念を行動へと根づかせていきます。
担当者が動きやすくなる裁量と信頼の設計
担当者の熱意を活かすためには、裁量の設計が重要です。ブランド施策を現場が推進できるよう、一定の判断権や実行権を持たせることで、「任されている」という自覚が生まれ、主体的な行動が育ちます。
一方で、経営層からの信頼のメッセージも欠かせません。「失敗しても挑戦を称える」文化をつくることで、担当者は安心して行動でき、ブランドを“自分ごと”として動かし始めます。
「評価制度」と「コミュニケーション設計」の工夫
ブランドの理念を根づかせるには、評価制度やコミュニケーションの仕組みとの一貫性が不可欠です。
理念に沿った行動を正しく評価する人事制度、現場の声を吸い上げて経営とつなぐミーティングデザイン、そして理念を軸に語り合う1on1や社内ピッチイベントなど。
“言葉”と“制度”をリンクさせることで、理念は単なるスローガンではなく、日々の判断を導く「企業文化」として定着します。
なぜ「想い」がブランドを育てるのか?

ブランドは、ロゴやデザインだけで形作られるものではありません。企業が「何を信じ、何のために存在するのか」という、深い理念とビジョンの結晶、それがブランドです。
この「想い」こそが、消費者の心を動かし、共感を呼び、ブランドとしての信頼を築きます。そしてこの想いを社会に伝え、実体験として浸透させる営みが、ブランディングです。
では、どうすればその想いを正しく、力強く伝えられるのか?
その答えはシンプルですがとても深く、経営者の揺るがぬ決意、現場担当者の情熱的な実行力が重なり合うことだと言えます。
トップが掲げるビジョンが明確であるほど、現場は自信を持って動けます。
現場の情熱が本気であればあるほど、その想いは社外へも鮮明に伝わります。
この両者のエネルギーが一致したとき、ブランドは真の力を持ち、市場の中で“選ばれる存在”へと成長するのです。
経営者の揺るがぬ決意とは?
経営者の「揺るがぬ決意」とは、変化の激しい時代にあっても、自社の存在意義やビジョンを明確に持ち、それを信じ抜き、実現し続ける覚悟です。それは単なるスローガンではなく、あらゆる判断・行動の“軸”として組織全体を導く力になります。
この決意には3つの要素があります。
1.理念を信じ抜く覚悟
どれだけ批判されても、流行が変わっても、「自社が目指す世界」に対する信念を手放さない。例えば、スティーブ・ジョブズが「直感的で美しい製品」に固執し続けたように。
2.困難を乗り越える胆力
ブランドが成長する過程には必ず障壁となる困難が訪れます。経営者の本当の姿勢が問われるのは、売上が下がった時、仲間が去った時、誤解された時など、困難に直面した時です。そんな時にもビジョンを曲げず、「なぜそれをやるのか」を語り続けられるか。それが決意の度合いだと言えます。
3.現場に希望と方向性を示す力
経営者の言葉が本気であれば、社員は迷いなく動けます。トップが揺るがなければ、現場も自信を持ってブランドを体現できます。
「ブランドの軸」になる経営者の決意

ブランドが強く育つ企業には、必ずと言っていいほど、明確な“志”を掲げるトップの存在があります。経営者が「自社は何のために存在し、どんな未来を実現したいのか」を自らの言葉で語り、社内外に示すこと。その覚悟あるメッセージこそが、ブランドの“軸”となり、すべての判断や行動の基準になります。
例えば、アップルのスティーブ・ジョブズは「人々の生活を変えるツールを創る」というビジョンを貫きました。
ユニクロの柳井正氏は「服を変え、常識を変え、世界を変える」という明快な使命を掲げました。
彼らのように、経営者自身がブランドの最初の体現者となり、理想を語り続けたからこそ、世界中に共感が広がったのです。
また、経営者の決意が組織全体に浸透すれば、社員一人ひとりが「何を基準に判断すべきか」が明確になり、ブランドに一貫性が生まれます。この一貫性こそが、顧客の信頼を築き、ブランド価値を積み重ねていく土台となるのです。
ブランドを“戦略”で終わらせないために必要なのは、トップの確固たる信念。
それはロゴやコピー以上に、ブランドの真の力を形づくる要素です。
◉Apple:スティーブ・ジョブズ氏のビジョンの本質
「テクノロジーを、人間のために美しく使いやすい形で提供する」
→ 単なる高性能ではなく、誰でも直感的に使える設計にこだわった。
「世界を変える製品をつくる」
→Mac、iPod、iPhone、iPadはすべて、その時代において「人々の常識を変える」存在となった。
「自分たちが本当に信じるものを、最高の形で世に出す」
→利益や市場調査に左右されず、「自分たちが欲しいもの」を追求した。
ジョブズは、ブランドとは“信念の塊”であると考えており、アップルはその信念を体現した存在でした。そのため、アップルのブランド戦略において最も重要だったのは、彼自身がブレないビジョンを持ち、それを語り続けたことにあります。
◉UNIQLO(ファーストリテイリング):柳井正氏のビジョンの核心
「服を変え、常識を変え、世界を変える。」このフレーズはユニクロの企業理念としても広く知られており、ユニクロというブランドの軸=柳井氏の信念を体現しています。
「単なる衣料品販売ではない」
→人々の暮らしをより良くする「ライフウェア」を提供。
→機能性・品質・価格のバランスにこだわり、日常を支える衣服を追求。
グローバルに通用する「新しい常識」をつくる
→欧米ブランドに挑戦するのではなく、「日本発で世界の新しいスタンダードを創る」姿勢。
→アパレルに限らず、「日本企業が世界でリーダーになるモデルを示す」こと。
社会・環境問題にも向き合う企業へ
→サステナビリティやダイバーシティにも積極的。
→単なるCSRではなく、事業活動そのものを通じて社会に貢献する姿勢。
「一番大切なのは、服を通じて人の生活をより良くするという志です。」
「世界の人々の役に立たないと、企業の存在意義はない。」
ユニクロのブランドの強さは、柳井氏のこのような長期的かつ普遍的な視点を持った決意に支えられています。
「ブランドを前進させる」担当者の熱意

一方ブランドは、経営者のビジョンだけでは形になりません。その“想い”を具体的な体験としてお客様に届けるのは、現場で日々動く担当者の存在です。
接客、商品企画、SNS発信、アフターサービス…。あらゆる接点での「担当者の行動」が、お客様にとってのブランドの印象を決定づけます。特に大切なのは、マニュアルに従うだけではなく、「自分ごと」として動く姿勢=主体性。ブランドに共感し、信じ、自らの言葉と行動で伝えようとするその熱意が、ブランド体験の質を高めていきます。
熱意は社内に波及し、ブランドを育てる
一人の担当者が、心からブランドを信じて行動する。
その姿勢は、周囲に驚くほど強い影響を与えます。
「ここまで本気でやっている人がいるなら、自分も応えたい。」
そんな共感が社内に広がり、やがてチーム全体を動かす原動力に変わっていきます。
この“熱意の連鎖”が生まれることで、ブランドに対する組織全体の“温度”が一気に高まり、挑戦を後押しする文化が生まれます。そしてその熱は、サービスや商品に表れ、結果として顧客の期待を超える価値提供へとつながります。
信頼と感動を呼ぶブランドの背景には、いつも“人の情熱”があるのです。
ブランドを動かすのは「人の想い」
ロゴやキャッチコピーがブランドの“顔”だとすれば、その中身をつくり、日々の実践で育てていくのは社員一人ひとりの行動と感情です。
理念やビジョンは掲げるだけでは意味がありません。
経営者がブランドの軸を明確に示し、担当者がその意図を汲み取り、熱意をもって動く。この連携があることで、ブランドは“飾り”ではなく、“生きた存在”として社会に機能し始めます。
人の想いがあるからこそ、ブランドは言葉を超えて、信頼や感動を生み出すことができるのです。
理念浸透に成功した企業の制作事例5選

理念を「掲げる言葉」から「感じる体験」へ。企業の想いをデザインで可視化し、社員や社会に共感として浸透させた事例を紹介します。
本質を掘り下げたMVV開発やロゴデザインを通じて、各社がどのように自らの価値観を形にし、文化として根づかせていったのか。理念を実践へと導いた、5つのブランドストーリーです。
MVV/ロゴ開発事例|株式会社アクティサポート
アクティサポートが掲げる新たなVALUEは、「力強い警備」と「美しい警備」。社会の安心を守る警備という職業に、力だけでなく品格をもたらすことを目指しました。
ロゴデザインは、その二つの価値観を象徴的に表すため、強さを感じさせる濃紺と、美しさを象徴する明るいブルーの2色で構成。2本の帯は“守る力”と“魅せる力”を表しながら、未来へとはためく旗をイメージしています。社員が掲げる「警備の質を誇れる会社でありたい」という想いを、社会へ堂々と示すフラッグとしてデザインしました。
誇りと信頼を感じさせるアイデンティティが、ブランド全体の方向性を明確にしています。
MVV/ロゴ開発事例|株式会社フロアエージェント
フロアエージェントのロゴは、最先端の技術力と職人技の融合をテーマに構築されました。ブランドの根幹である「技術」と「技能」を、2本の異なる柱としてデザイン。
先進性を象徴するブルーはテクノロジーの冷静な知性を、コンクリートを想起させるグレーは熟練の現場力を意味しています。2色の柱が交わることで、機械的でも感覚的でもない“融合の美学”を体現。常に進化し、挑戦し続ける同社の姿勢を、上昇するフォルムで表現しました。
ロゴは単なるシンボルではなく、企業が未来へ向かって進化し続ける意志を示す“ビジョンの旗印”として機能しています。
コンセプト/ネーミング/ロゴ開発事例|日進医療器株式会社[NACTUS]
医療器具ブランド「NACTUS」は、使いやすさと機能美を追求したブランドコンセプトのもと誕生しました。
青みがかったグレーを基調としたロゴマークは、先進性と信頼感を同時に感じさせるカラー設計。曲線と直線が調和したフォルムは、車いすとしての滑らかな操作性と、精密な技術力を象徴しています。そのラインには、“人に寄り添うやさしさ”と“ものづくりへの誇り”の両立というNACTUSの哲学が込められています。
ネーミングも「Nurture(育む)+Active(能動的)」を由来とし、使用者の生活を支え、動きを育む存在であることを表現。医療の現場に、新しいデザイン価値をもたらすブランドとして確立しました。
ブランドコンセプト/ロゴ開発事例|東京海上日動メディカルサービス株式会社
「健康未来®︎」を掲げる東京海上日動メディカルサービス(TMS)は、健康経営のパートナーとして企業や健保組合を支える存在です。しかし、理念が社内に十分に浸透していないという課題を抱えていました。
そこで実施したのが、社員参加型のワークショップ。
メンバー自身が“健康未来とは何か”を再定義するプロセスを通じて、ブランドの根幹であるMI(Mission・Identity)とVI(Visual Identity)を再構築しました。
ロゴやビジュアルは、TMSが寄り添い支える姿を象徴する柔らかなラインと温かなトーンで設計。理念を「掲げる言葉」から「行動する文化」へと昇華させるリブランディングとなりました。
MVV/ロゴ開発事例|ゆめいろ・なないろ保育園
ゆめいろ・なないろ保育園のロゴ開発では、「いろ=個性」「なないろ=多様性」という園名の意味から出発しました。
キーワードは“寄り添う”“のびのび”“育ち合う”。これらをビジュアル化するため、子どもたち一人ひとりの個性を10粒の「種」で表現しました。形も色も異なる種たちが、輪となって寄り添いながら成長する姿は、多様な個性が共に育つ園の理念そのものです。
やさしいトーンの配色は、子どもを見守る保育士のまなざしをイメージ。ロゴは単なる園の印ではなく、“人を育て、心を育てる”という教育の信念を可視化したシンボルとして、保護者・地域からも温かく受け入れられています。
今日から始める理念浸透5ステップ
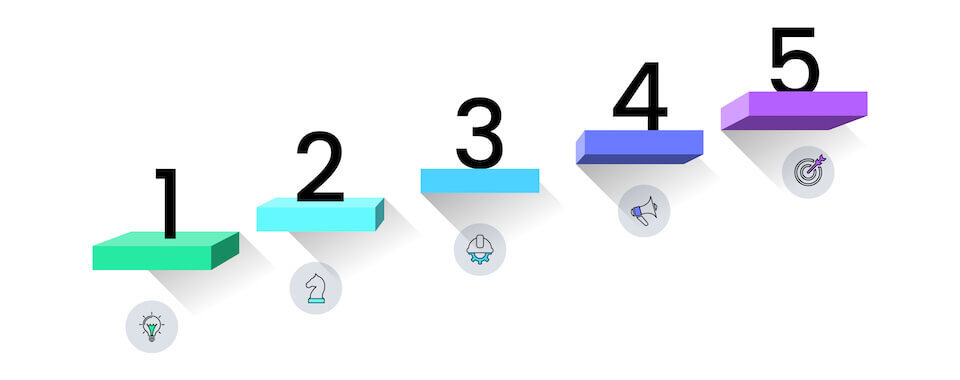
理念を社内に根づかせる取り組みは、時間をかけた意識改革だけではありません。小さな実践の積み重ねこそが、理念を“文化”へと変えていきます。経営者の想いを社員が自らの言葉で語り、行動に変えるために。ここでは、今日から始められる理念浸透の5つのステップを紹介します。
Step1.社員とともに考える/理念は“共感”から生まれる。
理念は、経営者が一方的に掲げるものではなく、社員とともに“つくり上げる”ものです。まず大切なのは、トップが想いを語り、社員が自分の言葉でそれを受け止め、議論し、再解釈する時間を持つこと。
ワークショップや対話の場を通じて、「私たちは何のために存在するのか」「どんな価値を社会に届けたいのか」を共に考えることで、理念は“他人の言葉”から“自分たちの信念”へと変わります。
理念の本質は「伝える」ではなく、「一緒に育てる」ことにあります。
Step2.理念を再定義する/変化の時代に、再び“原点”を問う。
理念は、策定して終わりではありません。時代や事業の変化に合わせ、何を守り、何を進化させるのかを見直す必要があります。
創業時の想い・これまでの歩み・これからの社会の変化を踏まえ、「いまの自社にとっての“存在意義”とは何か?」を言語化し定期的に見直すことで、常にブランドの軸が明確化されます。
再定義は、過去を否定することではなく、未来に向けて理念を“更新”する営み。これにより、社員一人ひとりが「この方向に進めばいい」と確信を持てるようになります。
Step3.クレド化する/理念を“行動の言葉”に翻訳する。
理念は美しい言葉であるほど、抽象的になりがちです。そこで必要なのが、「日常でどう動けば理念を体現できるか」を具体化するクレド(信条)化です。クレドは、社員の行動基準であり、現場判断の“羅針盤”になります。
例えば、「誠実に対応する」ではなく、「相手の立場に立って3秒考えてから返す」といった具合に、行動に移しやすい表現へと落とし込むことが重要です。理念を“使える言葉”に変えることで、社員は迷わず理念を実践できるようになります。
Step4.共有の場をつくる/理念を語り、感じ、育て合う文化へ。
理念は“掲げる”だけでは浸透しません。語り合い、感じ合い、共感し合うことで初めて「文化」として根づきます。朝礼や1on1、全社会議、社内報など、日常のあらゆるシーンを活用して理念を繰り返し共有しましょう。
また、社員が理念を体現したエピソードを紹介する「理念アワード」や「クレドピッチ」などの仕組みを設けると、理念が生きた言葉として社内に循環します。理念は、一度伝えるものではなく、何度も“再発見されるもの”です。
Step5.理念をデザインする/言葉を、行動と体験に変える。
理念の浸透は、言葉で終わらせては意味がありません。
社員も顧客も、日々の行動や空間、プロダクトやサービスの中でその理念を“感じられる状態”にすることが大切です。それが「理念をデザインする」という発想です。
たとえば、オフィスの空間デザインに理念を反映させる。採用サイトやパンフレット、映像やノベルティなどのクリエイティブに、理念の世界観を込める。制服、言葉遣い、社内イベント、ブランドムービーなど、あらゆるタッチポイントが“理念の体現”の場となります。
理念をデザインすることで、組織全体のトーン&マナーが統一され、社員が“この会社らしさ”を自然に纏うようになります。それは顧客や社会にとっても、“ブランドとしての信頼と誠実さ”を感じる瞬間につながります。
理念をデザインするとは、理念を「伝える」から「感じさせる」へ進化させること。
理念をデザインできた企業は、理念が単なるスローガンではなく、“生きたブランド文化”として息づいていきます。
まとめ:理念を動かすのは仕組みと人
ブランドは、経営者の決意から始まり、担当者の情熱によって動きます。そして、その熱を継続的に循環させるのは“仕組み”です。MVVとクレド、共有の場、裁量設計、評価制度。これらをつなぐ設計こそが、ブランドを「語られる存在」から「生き続ける文化」へと進化させる重要ポイントです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。










