
135
社員の挑戦を促す組織文化とブランディングのつくり方
挑戦を応援する企業こそ、未来を創る
社員一人ひとりが挑戦できる環境づくりが、企業の価値とブランドを高めます。
「挑戦できる文化」が必要な3つの理由
〜なぜ今、組織に挑戦の土壌が求められるのか〜
企業が持続的に成長し、変化の激しい社会で生き残るためには、社員一人ひとりが自ら考え、行動し、新たな価値を創造していく力が不可欠です。こうした力を育むには、社員が失敗を恐れずに挑戦できる「文化」が土台として必要です。
まずは、「挑戦できる文化」が今なぜ企業に求められているのかを、以下3つの観点から紐解いていきます。

1.現代のビジネス環境における変化のスピード
テクノロジーの進化、顧客ニーズの多様化、国際情勢の変化など、現代のビジネス環境はかつてないほどのスピードで変動しています。こうした環境下では、過去の成功体験や既存のビジネスモデルに固執していては、すぐに市場から取り残されてしまいます。
社員一人ひとりが新しいアイデアに挑戦し、小さな実験を繰り返すことで、変化に柔軟に対応できる組織が形成されます。挑戦する文化は、企業の競争力を維持・強化するための「生存戦略」でもあるのです。
2.若手人材の価値観の変化(成長・挑戦への欲求)
近年の若手世代は、「安定」よりも「成長」や「自己実現」に重きを置く傾向が強まっています。企業に対しても、単に与えられた業務をこなす場ではなく、自分のアイデアを形にできる環境や、新しいことに挑戦できる風土を求めています。
このような価値観の変化に応えられない企業は、優秀な人材の確保・定着が難しくなります。社員の挑戦を後押しする文化の醸成は、採用力やエンゲージメント向上に直結する、戦略的な取り組みと言えるでしょう。
3.旧来の企業文化によるリスク(硬直化、離職率上昇)
年功序列、失敗への過剰な批判、トップダウン型の意思決定。こうした旧来の企業文化が残る組織では、社員の自発性が損なわれ、挑戦意欲も自然と薄れてしまいます。
その結果、組織全体が硬直化し、イノベーションが生まれにくくなるだけでなく、成長機会を求める社員が離職するリスクも高まります。特に、挑戦を歓迎しない職場環境は「停滞感」や「閉塞感」を生み出しやすく、企業イメージやブランディングにもマイナスの影響を及ぼします。
このように、「挑戦できる文化」は、変化への対応力、人材の確保・育成、そして持続的な成長のために不可欠な要素です。
社員が挑戦しなくなる3つの無意識

組織の停滞は「社員が挑戦しないこと」から始まります。しかし、その原因は個々の能力不足ではなく、職場環境に刷り込まれた無意識の心理にあります。社員は過去の経験や職場の空気から「恐れ」「諦め」「逃げ」という感情を身につけ、やがて新しい提案や行動を避けるようになります。経営者にとって重要なのは、この無意識の壁を見抜き、挑戦を促す文化へと変革することです。これは単なる人材育成の話ではなく、企業の持続的な成長を左右する経営課題です。
1.恐れ:「評価が怖い」「否定されたくない」
社員が新しい提案や行動に消極的になる最も大きな理由の一つが、「否定されること」や「評価が下がること」への恐れです。特に過去に意見を却下された、ミスを厳しく叱責された、上司に冷たくあしらわれたなどの経験がある場合、その記憶は無意識のブレーキとなって残ります。
この「恐れ」は、職場の雰囲気や上司の姿勢によって強化されることが多く、「何も言わなければ安全」という防衛反応へとつながります。こうして社員は徐々に声を上げなくなり、挑戦や創意工夫が失われていきます。
2.諦め:「言っても無駄」「どうせ上が決める」
「どうせ意見を出しても変わらない」「上層部の決定には逆らえない」と社員が感じていると、やがて提案そのものをやめてしまいます。このような諦めの感情は、過去の経験や組織の意思決定プロセスの透明性の欠如から生まれます。
例えば、現場からの提案が形だけで終わったり、トップダウンの意思決定が常態化していると、「社員の声は軽視されている」と受け取られてしまいます。この「諦め」が広がると、社員は自ら動くことをやめ、「言われたことだけをやる」スタイルに退行してしまいます。
3.逃げ:「波風立てない方がいい」「黙っていれば安全」
組織内の人間関係や力学に敏感な社員ほど、「目立たない方が得策だ」「異論を唱えると扱いが面倒になる」といった空気を感じ取り、無意識に“挑戦から逃げる”ようになります。特に日本企業に見られる「和」を重んじる風土が、この傾向を助長することもあります。
挑戦や提案が「空気を乱すもの」とみなされる職場では、自然と保守的な行動が選ばれ、安定を優先するムードが支配的になります。これは一見「調和」のようでいて、実はイノベーションや組織の活性化を阻害する重大な要因です。
こうした「恐れ・諦め・逃げ」の感情は、社員が生まれ持った特性ではなく、日々の職場体験の積み重ねが無意識に刷り込んだものです。この負のループを断ち切り、挑戦を促す文化へと転換するには、経営層・管理職・人事が一体となった意識改革と仕組みづくりが必要です。
挑戦を促す文化構築 4つの施策

社員が自ら挑戦し、変化に前向きに向き合える組織には、共通して「挑戦を後押しする文化」が存在します。
この文化は単なる精神論ではなく、具体的な環境・制度・関係性の中で醸成されるものです。逆に言えば、意図的に仕組みを整えることで、どの組織でも挑戦を促す土壌を築くことが可能です。
ここでは、組織に「挑戦文化」を根付かせるために特に有効な4つの施策を紹介します。それぞれが独立しながらも相互に作用し、挑戦が自然と生まれる組織づくりに寄与します。
1.心理的安全性の確保
社員が「こんなことを言ったらどう思われるだろう」「失敗したら評価が下がるのでは」と感じている限り、挑戦は生まれません。心理的安全性とは、立場や年次に関わらず、自分の意見を自由に発言でき、間違いや失敗をしても人格を否定されない安心感のことです。
この安全な環境が整うことで、社員は自らの考えを臆せずに表現し、新しい取り組みにも積極的にチャレンジできるようになります。会議での発言の受け止め方や、上司の傾聴姿勢が、この文化の土台となります。
2.失敗を許容する仕組み(失敗共有会、賞賛文化など)
挑戦には失敗がつきものです。しかし、日本企業では「失敗=評価が下がるもの」というネガティブなイメージが根強く、社員の挑戦意欲を奪っています。
これを打破するには、失敗を成長の一部と捉え、前向きに共有する仕組みづくりが効果的です。たとえば、失敗事例をオープンに語り合う「失敗共有会」や、失敗しても挑戦したこと自体を称える「チャレンジ賞」など、ポジティブなフィードバック文化が社員の意識を変えていきます。
3.チャレンジ支援制度(提案制度、社内スタートアップ支援)
制度として社員の挑戦を後押しする仕組みを整えることも重要です。たとえば、誰でもアイデアを提出できる提案制度や、実際に新規事業を立ち上げる機会を与える社内スタートアップ支援など、社員の「やってみたい!」を具体的に形にする場が必要です。
これにより、社員は単なる「業務遂行者」ではなく、「価値創造の当事者」としての意識を持つようになります。特に、アイデアが実現に向かう成功体験を得られれば、挑戦することが自律的な習慣として根付いていきます。
4.キャリア自律支援(副業・越境学習)
「会社の枠の中」だけでなく、個人が自らのキャリアを切り拓いていける環境づくりも、挑戦文化には欠かせません。副業や兼業の容認、他業界・他社とのプロジェクトへの参画(越境学習)など、社員が外の世界に触れ、新たな視点を得られる機会を提供することが重要です。
このような取り組みは、社員の成長意欲を刺激すると同時に、企業にも多様な知見やネットワークが還元されるという好循環を生み出します。挑戦することが“会社のため”ではなく、“自分の人生のため”でもあると実感できる支援が、組織の活力を根本から変えていきます。
これら4つの施策は、それぞれが独立した取り組みでありながら、組み合わせて実行することで相乗効果を生み出します。心理的に安全な職場環境があるからこそ、失敗も受け入れられ、制度があるからこそ挑戦の機会が増え、キャリア支援があるからこそ社員の視野も広がる。そうした好循環が、組織全体に活力をもたらします。
挑戦する社員が育ち、挑戦を支える仕組みがあり、挑戦を称賛する文化がある。そんな環境こそが、企業のブランド価値を高め、持続的な成長を可能にする土壌となります。
挑戦文化を根付かせる5つのブランディング施策
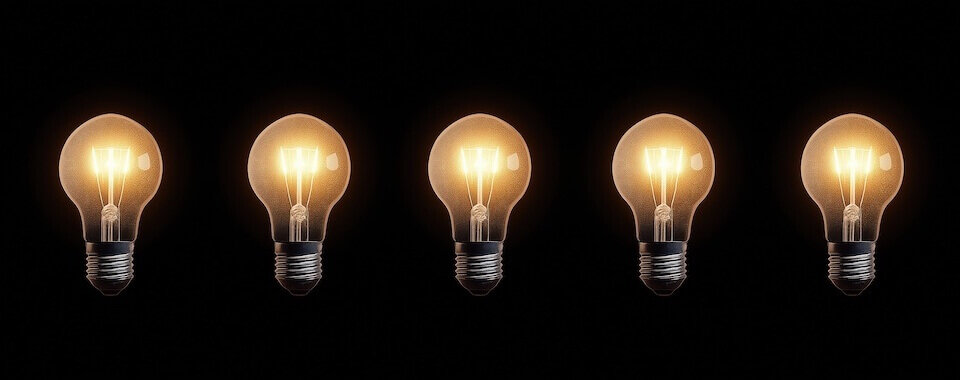
組織に挑戦の文化を根付かせるためには、制度や仕組みだけでなく、社員の意識や行動を形づくる“ブランドの力”を活用することが重要です。
つまり、「自分たちの会社は挑戦を大切にしている」という共通認識をつくり、行動にまで落とし込むブランディング戦略が不可欠なのです。
この章では、挑戦文化を育むうえで軸となる5つのブランディング施策を紹介します。社内外へのメッセージの発信、評価の設計、人材採用までを含めた、戦略的な文化浸透の方法です。
1.挑戦を「賞賛」するメッセージを掲げる
挑戦文化を根付かせる第一歩は、「挑戦こそが価値である」という明確なメッセージを社内外に発信することです。経営者の言葉や社内のスローガン、企業理念の中に“挑戦”を明記することで、社員にとって挑戦が「求められる行動」であるという認識が育ちます。
また、行動指針や行動評価の中にも挑戦を称える言葉を入れることで、日々の業務の中でも挑戦が「当たり前の価値」として意識されるようになります。メッセージは企業のブランディングの核であり、文化を動かす力を持ちます。
《関連サービス》
インナーブランディング
2.挑戦を「評価」する仕組みを構築する
挑戦が奨励されても、評価されない環境では長続きしません。挑戦の成果だけでなく、「行動そのもの」を評価対象とする人事制度や、リスクを取った挑戦に対する特別表彰などの仕組みが求められます。
「結果が出なかったとしても、挑戦したこと自体が価値」とする評価軸を明確にすることで、社員は安心してチャレンジできるようになります。挑戦を“行動指標”として組み込み、マネジメントに浸透させることがブランディング施策として不可欠です。
《関連サービス》
ブランディングコンサル支援/相談
3.挑戦を「共有」する組織体制を築く
挑戦事例が社内に共有されないまま埋もれてしまうと、他の社員にとっての学びやモチベーションになりません。挑戦のプロセスや失敗談、学びをオープンに共有できる文化と仕組みが必要です。
社内報やイントラネット、ピアボーナス制度、朝会・夕会などを活用し、部署や役職を越えて挑戦を語り合える場を設けましょう。挑戦が「見える化」されることで、社員の行動は刺激され、挑戦が次々と連鎖していきます。
《関連サービス》
インナーブランディング
4.挑戦を「発信」する仕組みをつくる
今の時代、社員の行動や雰囲気はSNSや口コミを通じてリアルに外部に伝わります。社内で挑戦が称賛され、可視化され、応援される姿があると、それはそのまま企業の「挑戦を大切にするブランド」として社会に伝わっていきます。
オウンドメディアやSNS、採用ページで社員の挑戦ストーリーを発信したり、社外向けイベントで若手社員が登壇するなど、外部への露出を設計することで、ブランディングとしての効果が高まります。企業の文化を「見える化」し、共感を得る発信は、採用力や企業イメージにも直結します。
《関連サービス》
企業ブランディング
5.挑戦する「人材」を獲得する
挑戦文化をつくるには、「挑戦したい」と思っている人材の獲得が最も近道だと言えます。そのためには、採用活動の段階から「私たちは挑戦を歓迎する会社です」と明確に伝える必要があります。
採用サイトや会社説明会、インターンシップなどの接点で、社員の挑戦事例を紹介し、会社のカルチャーとして挑戦が根付いていることを打ち出しましょう。また、選考プロセスの中でも「挑戦経験」や「挑戦意欲」を問うことで、文化にフィットする人材とのマッチングを高めることができます。
《関連サービス》
採用ブランディング
ブランディングに向けたミッション&ロゴ開発事例5選

企業ブランディングにおいて、「ミッション」と「ロゴ」は組織の存在意義や価値観を視覚的・言語的に伝える最も重要な要素です。変化の激しい現代において、自社の個性や志を明確に伝えるためには、しっかりとしたブランドアイデンティティの構築が欠かせません。
ここでは、実際に企業のミッションとロゴ開発を通じてブランディングを強化した5つの事例をご紹介します。それぞれの企業がどのような想いを込めてミッションを再定義し、ロゴにどのような意味やデザイン哲学を込めたのかを、具体的なストーリーとともにお届けします。
いい未来を、いい警備から|株式会社アクティサポート
新たに開発したアクティサポートのVALUEは「力強い警備」と「美しい警備」。そのアイデンティティのシンボルとなるロゴデザインは、警備の質の高さ(強さ)とスマートさ(美しさ)を兼ね備えた警備会社であることを2色の帯で表現しました。アクティサポートの警備の特徴を世の中に掲げる意味も込めて、フラッグに見立てたデザインにしています。
Quest for Next|三洋貿易株式会社
動的で勢いのあるフォルムで、一歩先をゆく先進性や進取の精神、現状にとどまらない変革への挑戦などを表現しています。ポジティブな未来をイメージした爽快なブルーをベースカラーとし、「i」の一部を、人の顔と地球(環境・グローバル) に見立ててグリーンに。「世の中の課題解決に貢献し、人と地球の笑顔をつくる」というVISIONの通り、「人と、地球と、より良い未来へ共に歩みを進めたい」という想いを込めています。
つなぎ、つくり、こたえる。|シモダL&C株式会社
100周年を機に定めたミッションを新ブランドとして体現するため、「挑む企業をつなぎ(Link)、革新をつくる(Create)」 の頭文字を採用した新社名「シモダL&C」をご提案。創業時より「シモダさん」と呼ばれ続けてきたお客様からの信頼と愛着が薄れないよう、旧社名:下田工業の「シモダ」を残すことで、創業者(下田利之様)が掲げた「企業は永遠なり」の精神を引き継ぎました。
ロゴデザインは、タイポグラフィのみで社名に加わった2つの事業の柱「L&C」を訴求。「L」と「C」を際立たせる事で、それぞれの事業成長や期待の大きさを表現。Lは「つなぐ」を象徴した「人」のシルエットを、Cは「つくる」を象徴した生み出す「手」を表現しました。
Connect & Delight|株式会社エフ・コード
SaaS事業「CODE Marketing Cloud」の開発及びWebコンサルティング事業を行う株式会社エフ・コード。IPOに向け他社との差別化を図り、企業価値を高めていく目的から企業ブランディングを実施しました。今回ご紹介するロゴは、同社が掲げるConnect(接続)&Delight(喜び)を具現化したもの。生産者の「価値あるものを届けたい」という思いと、生活者の「価値あるものに出会いたい」という思いをつなぎ、喜びを産み出すことで世界をより豊かにする様をシンボルとしてデザインしました。
ひとつの健康、ひろがる未来。|東京海上日動メディカルサービス株式会社
企業・健康保険組合様のお悩みや課題に応え、幅広いサービスで「健康経営」「健康増進」のコンサルティングを行う東京海上日動メディカルサービス(TMS)。すでに策定された「健康未来®︎」というメッセージが浸透していないことに課題を感じていました。そこで、社員によるワークショップを実施し、MI/VIの再構築をご提案。「健康未来®︎」をひもとき、全社員が同じ方向に向かえるようリブランディングを行いました。
経営陣と人事の役割〜挑戦文化を支える3つの柱〜

社員が安心して挑戦し、失敗から学び、主体的に成長していくためには、その挑戦を支える「土台」となる文化や仕組みの構築が不可欠です。そして、その文化を形づくるのは、経営者のビジョン、中間管理職のマネジメント、人事の制度設計といった、組織を構成する中枢の連携です。
挑戦文化は、スローガンだけでは根づきません。トップの言葉と行動、現場のマネジメント、制度の裏付けが揃ってはじめて、本物の文化となります。
ここでは、挑戦を当たり前にする組織に必要な3つの柱「経営」「管理職」「人事」の役割について詳しく解説します。
1.経営者のビジョンと言葉の力
挑戦文化を組織に根付かせるには、経営者自身が「挑戦」に対する価値観と覚悟を明確に打ち出すことが必要です。ビジョンや理念に「挑戦」の意味づけを明記し、言葉として繰り返し発信することで、社員の心に“経営の本気”が届きます。
特に、挑戦によって得られる未来の価値や、挑戦する人への期待をトップ自らが語ることには、何よりの説得力があります。また、経営者自身が失敗や挑戦をオープンに語る姿勢は、組織全体の心理的安全性を高め、社員の行動変容を促す起点になります。
2.中間管理職の意識改革
経営層の想いを現場に届け、日々の業務の中で挑戦を支える存在が中間管理職(マネージャー層)です。しかし、ここに“意識の壁”があると、挑戦文化は根付きません。
たとえば、「成果だけを求める」「失敗を許容しない」「前例に従うことを重視する」といった古いマネジメントスタイルが残っていれば、社員は挑戦よりも安全な行動を選ぶようになります。
マネージャーに求められるのは、部下の挑戦を引き出す問いかけ・承認・対話のスキルです。中間管理職自身が挑戦の意義を理解し、行動を変えることが、組織全体に“挑戦を後押しする空気”を広げるカギとなります。
3.人事が設計すべき仕組みと運用支援
人事部門の役割は、挑戦を支える制度・仕組みを設計し、組織全体が自律的に動けるよう運用を支援することにあります。たとえば以下のような施策が重要だと言えます。
・挑戦を促す人事評価制度(行動評価・失敗賞与など)
・キャリア自律支援(副業・研修・越境学習)
・提案制度や社内チャレンジ枠の設計
・心理的安全性を高める対話研修や1on1支援
・挑戦事例の可視化・共有フローの構築
単に制度をつくるだけではなく、現場で機能させるための運用設計・マネジメント支援・カルチャー浸透まで一貫して伴走することが、人事の真の価値となります。
挑戦文化の実現は、社員一人ひとりの意識改革だけで成し遂げられるものではありません。経営者が旗を掲げ、中間管理職が風を送り、人事が土壌を整えるという三位一体の取り組みがあってこそ文化は根づき、機能します。
企業の未来を切り拓くのは「挑戦する組織」です。そして、その組織をつくるのは、一人ひとりの挑戦を支える環境と仕組み、そして信頼です。
経営・現場・人事が同じ方向を向き、連携して“挑戦を後押しする力”を最大化していくことが、これからの企業ブランディングと成長の要となるでしょう。
まとめ:ブランディングの本質は「人がつくるブランド」です
〜“文化”がブランドをつくり、“人”が文化を動かす〜
企業ブランディングというと、ロゴ、コピー、広告、デザインなど「外向きのイメージづくり」が連想されがちです。
しかし、真に強いブランドとは、社員一人ひとりの行動や姿勢、そして社内に根づく文化から自然と生まれるものです。
特に、社員がイキイキと挑戦し、自ら価値を創り出そうとする姿は、どんな広告よりも企業の魅力を雄弁に物語ります。そうした姿が社内外に共有され、共感を呼び、信頼につながっていくことこそが、ブランドの根幹です。
だからこそ、挑戦を後押しする文化を育てることは、企業の持続的成長を支える土台となり、結果としてブランド価値の最大化につながります。
社員が「自分の会社を誇れる」状態こそが、最も強力なブランディングなのです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。










