
165
経営者と社員の考え方の違いと、経営幹部育成・組織強化のポイント
“やらされ感”から“やりたい組織”へ
幹部の意識転換や仕組みづくりを通じて、変化に強い持続成長型の会社を目指す具体策をご紹介します。
経営者と社員の考え方の違い
経営者と社員では、その立場や果たすべき役割が大きく異なるため、自然と考え方や価値観に違いが生まれます。この違いを意識せず放置してしまうと、次第に「温度差」や「認識のズレ」、「不信感」といった問題につながりかねません。
だからこそ、両者が互いの考え方や視点を意図的に共有し、理解を深める場づくりがとても重要になります。ここでは、代表的な違いを5つの観点で整理します。

①視野・時間軸の違い
《経営者》
常に中長期的な視点で物事を考えています。会社全体の成長や持続可能性、市場での競争力といった未来を見据えた課題や機会を重視します。
《社員》
比較的短期的な視点で考えることが多く、目の前の業務の達成や自分の役割・評価、職場の働きやすさなど、日々の仕事に重きを置く傾向があります。
②リスクに対する意識の違い
《経営者》
事業投資や新しい取り組み、人材登用など、リスクを伴う挑戦を積極的に行う必要があります。そのため、リスクを前提とした意思決定が求められます。
《社員》
一般的にはリスクを避けたいという意識が強く、安定や安心を求める傾向があります。大きな変化や未知の取り組みに対しては慎重になりやすいものです。
③責任の範囲の違い
《経営者》
雇用や財務、社会的責任など、会社全体に対する責任を負います。経営の意思決定一つひとつが、全社員や社会に対して影響を及ぼすことを常に意識しています。
《社員》
自身の担当する業務やチーム単位での責任意識が中心であり、会社全体の責任まで意識が及ぶことはあまりありません。
④お金・利益に対する意識の違い
《経営者》
会社の利益や資金繰りが事業継続の生命線であることを深く理解しています。利益が出なければ自らの報酬も得られないため、常に経営的な視点で数字を意識しています。
《社員》
給料や待遇面には敏感でも、会社全体の利益構造や資金繰りに対する関心は薄い場合が多く、その意識に差が生じやすいポイントです。
⑤変化に対する考え方
《経営者》
時代や市場の変化に柔軟に対応し、組織や事業そのものを変革していく必要性を常に感じています。変化は成長や存続のための前提と捉えています。
《社員》
現状維持を望む意識が働きやすく、変化には抵抗感を抱くことが多くあります。特に安定した環境を好む社員ほど、新たな取り組みに慎重になる傾向があります。
経営幹部育成の壁と意識転換の重要性
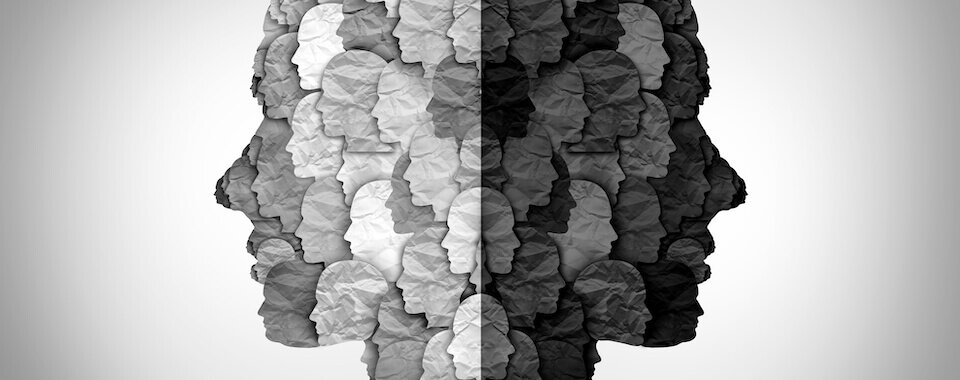
プレイヤー時代に大きな成果を上げた社員が経営幹部に昇進しても、必ずしも「経営的な成長」を遂げられるとは限りません。その背景には、「経営者」と「社員」ではまったく異なる基準や価値観で仕事に向き合っているという根本的な違いがあります。
この違いを理解しないままでは、幹部社員は「プレイヤー」としての意識にとどまり、本来求められる経営視点での行動や判断ができないままとなりがちです。
その結果、役割に対する誤解や社長との意識のズレが生まれ、会社の成長の足かせになってしまうことも少なくありません。
①経営陣と社員の働き方の違い
《経営者》
・役割:人を動かして結果を出す
・給料意識:給料は「払うもの」(赤字時は自分の給与なし)
・評価意識:社会・世の中から評価されたい
《社員》
・役割:自分が動いて結果を出す
・給料意識:給料は「もらうもの」(または稼ぐもの)
・評価意識:上司・周囲から評価されたい
②幹部に求められる3つの意識転換
1.経営者的な価値観や視点は自然には身につかない
経営層として求められる判断軸は、これまでの社員経験だけでは培われにくいため、意識的な学びや気づきが不可欠です。
2.基準・価値観の切り替え
会社全体や市場、社会の視点で物事を考える「基準」を自ら切り替えていく必要があります。
3.「自分は経営者である」という強い自覚を持つ
経営の一翼を担う存在としての自覚を持つことで、初めて行動や言動が経営レベルに引き上げられていきます。
◉目指す状態
・社長に指示されなくても、幹部自らが主体となって事業成長を推進している
・経営に近い視座で意思決定ができる社員が育ち、社長の負担が軽減されている
・社長自身が「会社の未来づくり」にエネルギーを注げるようになっている
このような幹部の意識転換が進むことで、経営者と幹部の間に強い信頼関係が築かれ、より一体感ある経営チームが生まれていきます。
古参メンバー問題と全世代巻き込みの組織強化策
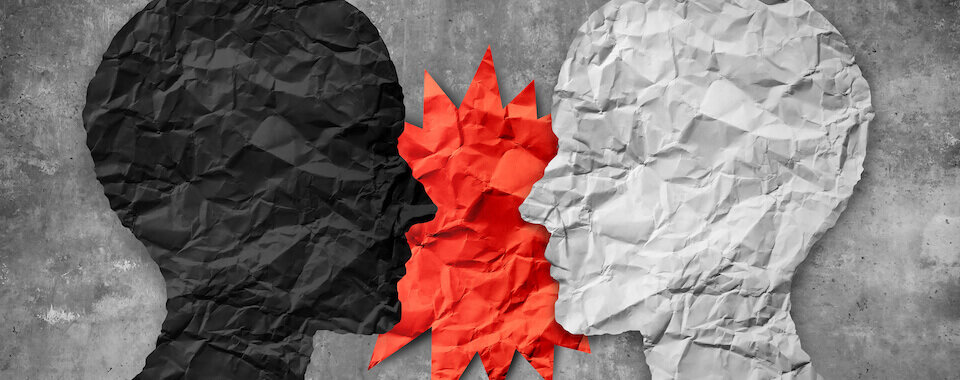
経営者が悩みやすいテーマの一つに「古参メンバーの扱い方」があります。長年会社に貢献してきた存在でありながら、その影響力の強さゆえに、組織の成長を妨げる一因になってしまうことも少なくありません。以下の状況が続くと、次世代の成長が停滞したり、組織全体の活力が損なわれたりするリスクがあります。よく見られる課題は以下の通りです。
①古参メンバーにありがちな3つの課題
1.昔のやり方に固執し、新しい考え方や若手の意見を受け入れない
長年の経験や成功体験があるがゆえに、これまでのやり方に強い自信や愛着を持っているケースが多く見られます。その結果、時代の変化や市場環境の変化、新しいテクノロジーなどを取り入れることに消極的になり、若手社員の柔軟な意見や新しい視点が組織に浸透しにくくなってしまいます。
2.若手社員の成長を積極的にサポートできず、足かせになってしまう
本来は先輩社員として、次世代を育てる役割が求められる立場にもかかわらず、自分のやり方に固執したり、若手の失敗を必要以上に否定したりすることで、若手社員が挑戦しづらい空気を生んでしまうことがあります。その結果、若手の成長が妨げられ、組織としての発展スピードが鈍化する恐れがあります。
3.本音で向き合おうとすると反発を招き、最悪の場合は退職につながる懸念がある
古参メンバーに対して、社長や上司が問題意識を率直に伝えたり、変化を求める働きかけを行ったりすると、自尊心を傷つけたり、自分の立場が脅かされると感じさせてしまうことがあります。
その結果、本人が反発したり、最悪の場合は組織から離れてしまうリスクが生じます。こうした状況を恐れるあまり、経営者側が古参メンバーに対して必要な対話や改善を先送りしてしまうケースも少なくありません。
②対処法:古参メンバーを巻き込みながら組織強化する3つの方法
1.役割転換で新たなやりがいをつくる
古参メンバーに「相談役」や「意思決定者育成」といった役割を与えることで、現役世代を支えるポジションへと意識をシフトさせ、新たなやりがいを提供する。
2.年齢の壁を取り払う
年齢や勤続年数による見えない役職制限を撤廃し、若手が挑戦しやすい文化を整えることで、全世代がフラットに意見を出せる環境をつくる。
3.挑戦心を引き出す
理想とする組織像を古参メンバーと共に描き、その実現に向けて彼ら自身にも貢献意欲を持ってもらう働きかけを行う。目的意識を共有することで、挑戦する意欲が高まる。
③組織強化に欠かせない2つの視点
1.デキる社員の定着
優秀な社員が「この会社でずっと働きたい」「ここで自分の力を発揮し続けたい」と思える組織文化を築くことが大切です。評価制度・キャリアパス・挑戦機会・心理的安全性など、多角的な工夫を通じて、貴重な人材が離職することなく、長期にわたり会社の成長に貢献してもらえる土壌を整えていきます。
2.イマイチ社員のパフォーマンス向上
いま一歩伸び悩んでいる社員や成長が停滞している社員にも、適切な成長機会やサポートを提供することが重要です。単に見放すのではなく、教育・育成・フィードバックを通じて成長意欲を引き出し、チーム全体のレベルを底上げしていくことで、組織全体としての強さや一体感が高まります。
この2つの視点をバランスよく取り入れることで、「一部の優秀な人材だけに依存した組織」ではなく、「全体の力が底上げされ、持続的に成長できる組織」を築いていくことができます。
社員の意欲とパフォーマンスを高める4つの仕組みづくり
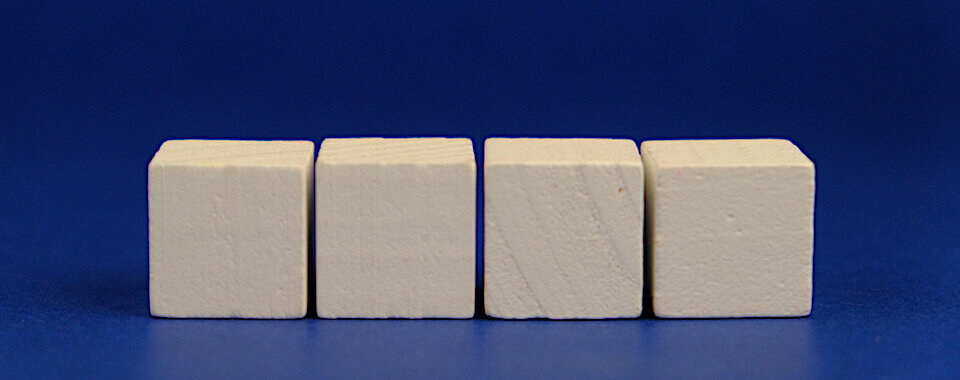
社員一人ひとりが意欲的に仕事に取り組み、組織全体の生産性とパフォーマンスを高めていくためには、単に制度や評価の整備だけでは不十分です。社員の内面から「やる気」や「納得感」を引き出す仕組みを意識的につくることが重要です。ここでは、実践的な4つの仕組みづくりご紹介します。
①「MUST」から「WANTS」で働く社員へ
社員が「やらなければならないから(MUST)」働くのではなく、「やりたい/挑戦したい(WANTS)」という主体的な意欲を持って働ける環境づくりが必要です。そのためには、個々の強みや関心を活かした仕事のアサインや、成長実感を得られる支援が求められます。
②イマイチ社員を引き上げる「10ヵ条」
一部の社員が成長意欲や成果の面で伸び悩むのは、組織にとって自然なことです。そうした社員にも、意図的に「成長のチャンス」や「改善のきっかけ」をつくることが大切です。
そのための具体的な行動指針(10ヵ条)を活用し、いま一歩の社員も引き上げ、組織全体の底上げを図ります。
③給与納得感を高める「年俸合意制度」
給与や評価に対する納得感は、社員のモチベーションや定着に大きく影響します。「年俸合意制度」は、人事メディアでも紹介されている先進的な評価手法であり、会社からの期待役割と社員自身の納得を事前にすり合わせたうえで年俸を合意する仕組みです。これにより、報酬に対する透明性と納得感が高まり、社員の働く意欲につながります。
④1on1面談による役割・目標共有
1on1面談を通じて、会社が社員に何を期待しているのか(期待役割・期待目標)を丁寧に共有します。あわせて、社員一人ひとりの状況や思いを汲み取り、本人が「納得感」を持って取り組めるようサポートします。
こうした定期的な対話は、信頼関係の醸成とやりがい向上に大きな効果を発揮します。
まとめ:経営者と社員の考え方の違いと、経営幹部育成・組織強化のポイント
経営者と社員の立場や考え方の違いを理解し、そのギャップを埋めるための意識改革と仕組みづくりが、持続的な成長を実現する重要なポイントとなります。幹部層の意識転換、古参メンバーの巻き込み、全社員の意欲とパフォーマンスを高める環境整備を通じて、“やらされ感”から“やりたい組織”へと進化させましょう。組織の一体感が高まり、変化に強く、次代へと成長を続けられる会社づくりのヒントとして、ぜひご活用ください。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。





