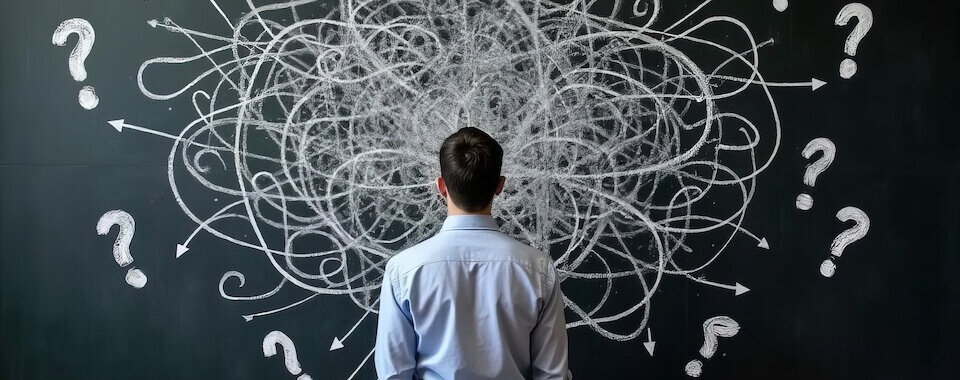
158
人材育成に潜む"9つの罠"
人材育成が変わる。“9つの罠”とその改善ポイント
育成施策にありがちな9つの罠とその改善ポイントを整理し、成果につながる育成のヒントをお届けします。
人材育成に潜む“9つの罠”
いま、多くの企業が人材育成に力を注いでいる一方で、「なかなか期待した成果につながらない」「育成効果が定着しない」といった悩みを抱えています。その背景には、企業が無意識のうちに陥りやすい“9つの罠”が存在します。
本コンテンツでは、一見よかれと思って実施している施策が、実は逆効果となってしまう典型的な例を整理し、より成果につながる育成のあり方や改善のヒントをお届けします。
1.そもそもの育成方針が存在しない
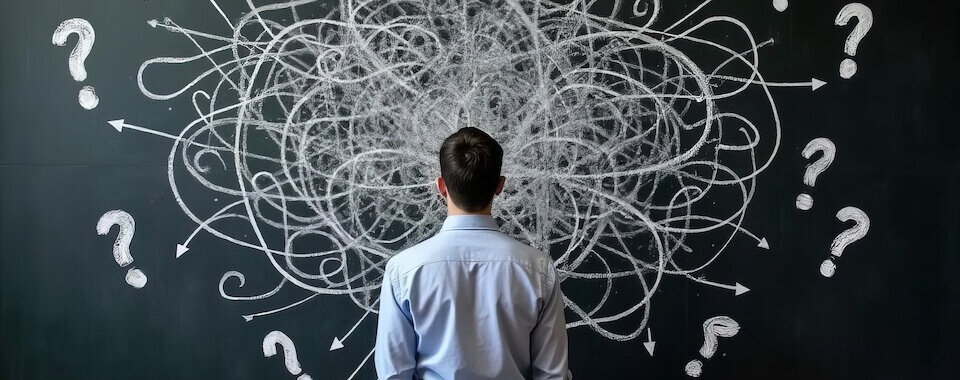
人材育成を行う上でまず重要となるのが「育成方針」の明確化です。しかし多くの現場では、どんな人材に育てたいのか、どのような能力や価値観を身につけてもらいたいのかといった基本方針が曖昧なまま、場当たり的に研修や教育を行ってしまうケースが見られます。
その結果、施策ごとの一貫性がなく、社員側も育成の目的を理解できず、成長の方向性が定まらないという状況に陥りがちです。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・経営戦略や企業理念とつながる「人材育成の基本方針」を策定する
・どのような人材像を目指すのか(コンピテンシーや価値観)を明文化する
・その方針に基づいた育成体系(研修・OJT・評価・フィードバックなど)を設計する
・育成の目的や方向性を管理職や現場社員とも共有し、一貫性のある育成を進める
2.現場任せのOJT育成になっている

OJT(On-the-Job Training)は実務を通じた効果的な育成手法ですが、現場に丸投げの状態になっていると、内容や質にばらつきが生じやすくなります。担当者によって教える内容や姿勢が異なり、教わる側も成長の方向性が見えづらくなるため、結果的に育成効果が低下してしまいます。
また、教える側に十分な育成スキルや意識が伴っていない場合、OJTが「単なる業務の手伝い」や「放置」になってしまうリスクもあります。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・OJTの目的や期待成果を明確にし、マニュアルや育成計画を整備する
・OJT担当者に対して指導スキルや育成マインドの教育を行う
・OJTとOFF-JT(集合研修や座学)を組み合わせ、体系的な育成につなげる
・OJTの進捗や学びを定期的に確認し、フォローアップの場を設ける
・OJTを「育成の場」として位置づけ、現場全体で育成意識を高める
3.画一的な研修で多様性をつぶしてしまう

同じ内容・同じ進め方の研修を一律に全社員に課すことで、個々の強みや多様な価値観が発揮されにくくなってしまうケースがあります。
特に、職種や経験、個人の成長段階を問わず一斉に実施される研修では、「誰にでも当てはまる無難な内容」になりやすく、結果として受講者の意欲や主体性を損なう可能性があります。本来、組織の競争力は多様な人材の個性や創造力に支えられています。画一的な育成は、それを阻害しかねません。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・職種、階層、キャリア段階に応じた「個別最適な育成プラン」を用意する
・選択型研修や自己選択型学習(リスキリング・自律学習)を組み込む
・画一的な研修だけでなく、OJTやメンター制度、対話型の場づくりを併用する
・個々の強みやキャリア志向に合わせて育成のアプローチを柔軟に設計する
4.「正解」を押し付け、自発性を奪ってしまう

研修や育成の場で「これが正しいやり方」「こうすべき」といった“正解”を一方的に教え込むスタイルは、受講者の考える力や主体性を奪ってしまう恐れがあります。
特に変化の激しい時代においては、状況に応じて自ら判断し、行動する力こそが求められます。「教わった通りにやる」ことが目的化してしまうと、柔軟な発想や創意工夫が生まれにくくなり、成長意欲の低下にもつながります。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・「教える」だけでなく「考えさせる」「問いを投げかける」スタイルを取り入れる
・ディスカッションやケーススタディなど、自主的に考える機会を増やす
・“唯一の正解はない”という前提で、多様な視点やアプローチを尊重する
・失敗から学ぶ文化や心理的安全性のある場をつくり、自発的な挑戦を促す
5.スキル重視でマインド醸成を軽視する

人材育成において、目に見える業務スキルや知識の習得に偏りがちになるケースは少なくありません。しかし、スキルは「なぜそれを行うのか」「どう成長したいのか」といった意識や価値観(マインド)が伴ってこそ、真に活かされるものです。
マインド醸成が置き去りにされると、学んだスキルも実践につながりにくく、行動変容や組織貢献といった成果に結びつきにくくなります。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・育成の中に「仕事観」「使命感」「組織理念との共感」を深める要素を組み込む
・ロールモデルとなる先輩社員や経営層との対話機会を設け、価値観や考え方を共有する
・スキルとマインドが結びついた育成体系(知識×行動×意識)を意識して設計する
・「どうありたいか」「何を大切にするか」といった内省を促すプログラムを取り入れる
6.評価とフィードバックが機能していない

育成の成果を高めるうえで欠かせないのが「適切な評価」と「タイムリーなフィードバック」です。しかし現場では、評価基準が曖昧だったり、年に一度の評価面談だけで終わっていたり、フィードバックが形骸化してしまっていることも少なくありません。
その結果、社員は「自分が何を期待されているのか」「どこを伸ばせばいいのか」が見えず、成長実感を持てなくなってしまいます。フィードバックが機能していない組織では、やがて育成の効果も頭打ちになります。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・評価基準(期待される行動や成果)を明確にし、全員に共有する
・フィードバックは年1回でなく、日常的な対話の中で行う文化をつくる
・単なる結果評価ではなく、努力やプロセスにもしっかり目を向ける
・フィードバックの質を高めるために、管理職へのトレーニングも実施する
・成長の方向性や次の目標を対話し、社員の主体的な成長意欲を引き出す
7.研修が場当たり的になっている

「とりあえず何かやらなければ」「流行のテーマだから」などの理由で個別の研修が企画されると、全体の育成方針や体系とのつながりが薄くなり、場当たり的な施策に陥ってしまいます。
このような状況では、受講者が「なぜこの研修を受けるのか」「自身の成長にどうつながるのか」を理解できず、学びが実務や行動変容に結びつきにくくなります。結果として、育成投資に対する効果も見えにくくなります。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・中長期的な視点で、企業理念や人材像に基づいた育成体系を整備する
・単発の研修に終わらず、スキルやマインドの段階的な習得を意識して設計する
・全体方針と各施策(研修・OJT・自己学習など)との連動性を高める
・企画段階で「誰に」「なぜ必要か」「どう活かすか」を明確にし、現場に共有する
・定期的に育成体系の見直しと更新を行い、時流や現場ニーズとのズレを防ぐ
8.育成が“人事部任せ”で現場の関与が薄い

人材育成を「人事部の仕事」と捉え、現場のマネジメント層や社員本人が主体的に関与しないケースは少なくありません。その結果、研修や制度が現場の実情やニーズと乖離し、現場の仕事に活かされにくい状況が生まれます。
また、現場マネージャーの育成意識が薄いままでは、日常の指導やフィードバックが機能せず、学びが職場に定着しにくくなります。育成は「全社の取り組み」であり、現場の関与と連携が不可欠です。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・育成方針や目的を現場マネジメント層と共有し、共通認識を持つ
・マネージャーにも育成責任と役割を明確にし、必要な教育や支援を行う
・現場と人事部が連携して育成施策を企画・運営する体制を整える
・OJTや1on1など、現場での日常的な育成を重視し仕組み化する
・育成の成果や好事例を現場にもフィードバックし、主体的な関与を促す
9.作りっぱなしで運用がされない
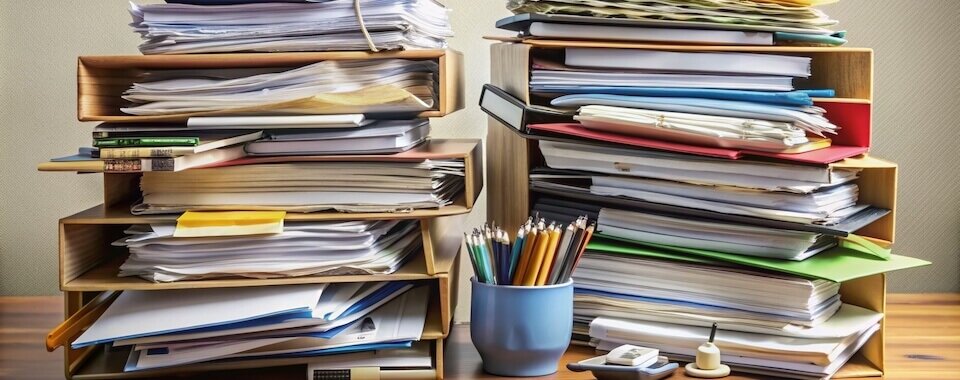
せっかく時間やコストをかけて作成した育成制度や研修プログラムも、現場に浸透せず形骸化してしまうことは珍しくありません。制度や教材が整備されても、運用ルールが曖昧だったり、現場への周知・定着が不足していたりすると「作りっぱなし」になり、成果につながらない状態に陥ります。
この状況が続くと「また新しい制度ができてもどうせ形だけ」といった形骸化した風土が生まれ、育成全体への信頼感も損なわれます。
《人材育成に向けた改善のポイント》
・運用ルールや実施フローを明文化し、現場にも丁寧に共有する
・担当部門や現場マネージャーの役割・責任を明確にする
・定期的な進捗確認やフォロー体制を整える(PDCAを回す)
・運用状況や成果を可視化し、必要に応じて柔軟に改善を図る
・制度導入時に「なぜやるのか」「何を目指すのか」を丁寧に伝え、当事者意識を醸成する
まとめ:人材育成に潜む“9つの罠”
いかがでしたでしょうか?人材育成は、一見正しく行われているようでいて、気づかないうちに“罠”に陥ってしまうことが少なくありません。今回ご紹介した9つの罠とその改善ポイントを参考に、自社の育成施策を今一度見直し、より効果的な人材育成へとつなげていただければ幸いです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
《関連するブランディング実績》
Prev
実践と研修で指導する能力開発
Next
社長依存の組織から社員主導型組織へ





