
160
組織拡大によって生じる社員との「8つのギャップ」と「改善策」
成長の壁を越える、成長ギャップと改善策
組織拡大で生まれやすい社長と社員のギャップと、その改善策を伝授します。
組織拡大によって生じる社員との「8つのギャップ」と「改善策」
企業が成長し組織が拡大する過程では、創業期にはなかった「社長と社員との意識や期待のズレ」が生まれやすくなります。社長は理念やビジョンを強く意識し成長戦略を進めたいと考える一方で、社員は現場での業務に追われ、変化への対応や将来への不安を抱えていることも少なくありません。このギャップを放置すると、組織の一体感やエンゲージメントの低下を招きかねません。
本コンテンツでは、組織拡大に伴って起こりやすい「8つのギャップ」とその具体的な改善策を整理し、成長フェーズに合ったより強い組織づくりのヒントをご紹介します。
1.ビジョン・理念の浸透度のギャップ

組織の成長とともに、社員の数や業務の幅が広がると、社長が大切にしている企業理念や将来ビジョンが、社員一人ひとりに十分に伝わらなくなることがあります。
特に現場の社員にとっては、日々の業務と理念やビジョンとのつながりが見えにくくなり、「理念は経営層だけが語るもの」と捉えられてしまうことも少なくありません。この状態が続くと、仕事に対する意義や目的意識が薄れ、組織としての一体感や求心力が低下してしまいます。
《ギャップ改善のポイント》
・企業理念やビジョンを「定期的に」「多様な手段で」発信する(社内報、全社集会、社長メッセージなど)
・理念やビジョンを、業務の現場レベルに落とし込み、社員が自分の仕事と結びつけて理解できるよう工夫する
・ミドルマネジメント層が理念・ビジョンを現場に語れるよう教育し、日々のマネジメントに取り入れる
・理念・ビジョンに基づいた行動や取り組みを評価・称賛する仕組みをつくる
・社員との対話の場を持ち、理念やビジョンについての理解度や意識を定期的に確認・フィードバックする
2.会社の成長スピードに対する意識のギャップ

組織が急成長している局面では、社長や経営層はスピーディな変革や意思決定を求めがちです。しかし現場の社員は、日々の業務やルーチンワークに追われる中で、変化のスピードについていけず、混乱したり、慎重・保守的な姿勢になってしまうことがあります。
このギャップが広がると、社長は「なぜ動きが遅いのか」と感じ、社員側は「なぜそんなに急かされるのか」と感じるようになり、双方の不信感や摩擦につながりかねません。
《ギャップ改善のポイント》
・会社の成長ステージや求めるスピード感を明確に言語化し、全社に共有する
・変化の背景や意図を丁寧に説明し、社員が納得感を持って取り組めるようにする
・変化に対応するための教育や情報提供(変化対応力・業務改善力の強化)を行う
・社員の声や現場の実情を把握し、スピード感と現実とのギャップを埋める対話を増やす
・「変化への挑戦」を評価・称賛する文化を醸成し、社員の前向きな姿勢を引き出す
3.会社規模に対する認識のギャップ

組織が成長し社員数が増えると、社長と社員の間で「自社は今どんな規模の会社なのか」に対する認識にズレが生じることがあります。社長は創業時の意識のまま、「まだスタートアップだからスピード優先・柔軟に動こう」と考えている一方で、社員はすでに組織として一定の規模感や安定性、整った制度やルールを求めていることが多くなります。
このギャップが大きくなると、社長は「自発的に動いてほしい」と期待し、社員は「もっと明確なルールや役割分担が必要だ」と不安を感じるようになり、働き方やマネジメントへの不満につながる恐れがあります。
《ギャップ改善のポイント》
・自社の成長段階や今後目指す組織像を明確にし、社員に繰り返し伝える
・「何を柔軟に進めるべきで、何を制度化・ルール化すべきか」の線引きを整理する
・成長ステージに応じた適切な制度整備(人事制度・評価・働き方ルールなど)を段階的に進める
・社員の声や現場ニーズを取り入れ、現状とのギャップを埋める対応を行う
・社長自身も「今の組織規模に合わせたマネジメントやコミュニケーションスタイル」を意識的に見直す
4.コミュニケーション量・質のギャップ

組織が小さいうちは社長と社員との距離が近く、日常的に直接会話ができていたため、意思疎通や信頼関係が自然と築かれていました。しかし、組織が拡大するにつれて、社長と社員との物理的・心理的な距離が広がり、社員は「言いたいことが言えない」「聞きたいことが聞けない」と感じるようになります。
結果として、現場の状況や社員の本音が経営層に届きにくくなり、経営の意図や判断も現場にうまく伝わらないというコミュニケーションの質的なギャップが生じていきます。
《ギャップ改善のポイント》
・社長が定期的に現場との対話の場を設ける(タウンホールミーティング、オープンドア活動、食事会など)
・公式・非公式の両方で、社員が気軽に意見を言える場やチャネルをつくる
・「双方向のコミュニケーション」を意識した仕組みづくり(社内アンケート、フィードバック機会など)
・ミドルマネジメント層の役割を強化し、現場の声を吸い上げ、経営層とつなぐ橋渡し役を担わせる
・社長や経営層が自ら「耳を傾ける姿勢」を日頃から示し、心理的安全性を高める
5.評価・期待に対するギャップ

社長や経営層は、組織の成長や変化に対応できる「主体的に考え、行動する社員」を求めているケースが多くあります。しかし、評価制度や日常のマネジメントが「言われたことを正確にこなす」ことを重視する形になっていると、社員は「決められたことをきちんとやっていれば良い」という受け止め方になりがちです。
このギャップが広がると、経営側は「もっと自律的に動いてほしい」と感じる一方、社員は「何を期待されているのかわからない」「頑張っても評価につながらない」と不満を募らせてしまいます。
《ギャップ改善のポイント》
・社長や経営層の「求める人材像」「評価したい行動」を言語化し、明確に共有する
・評価制度の中に「主体性」「チャレンジ精神」を反映させ、評価対象とする
・マネージャー層が日々の面談やフィードバックで「自律的な行動」を促す意識づけを行う
・「チャレンジした結果」を適切に評価・称賛し、行動変容につなげる文化を育てる
・社員の理解度や納得感を確認しながら、評価制度や運用を柔軟に改善していく
6.業務の優先順位に対するギャップ
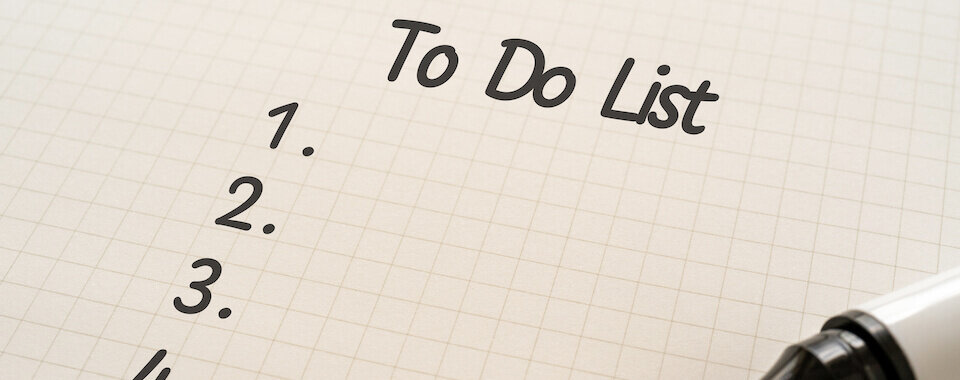
社長や経営層は、企業の成長や競争力強化のために、中長期の戦略的な取り組みや組織変革に意識が向いています。
一方、現場の社員は、日々の業務処理や直近の売上目標に追われており、長期的な視点や変革の意義を十分に理解・共有できていないことが少なくありません。
このギャップが広がると、社長は「なぜ変革が進まないのか」と感じ、社員側は「今はそれどころではない」と意識のズレが生じ、結果として重要な取り組みが進みにくくなるという悪循環に陥ります。
《ギャップ改善のポイント》
・中長期戦略や変革の必要性と背景を丁寧に説明し、社員の理解を深める
・経営目標と現場目標(短期・長期)のバランスをとったマネジメントを行う
・中長期的な視点を持てるよう、教育や意識づけの機会を設ける
・変革の進捗や成果を可視化し、社員の貢献実感を高める
・現場の業務負荷やリソース状況を踏まえ、変革への取り組み方を柔軟に調整する
7.成長機会やキャリアに対するギャップ

社長や経営層は「社員にはこの会社の中で大きく成長し、活躍してほしい」と強く願っていても、その意図や機会が社員に十分に伝わっていないケースがあります。社員側は、社内に明確なキャリアパスや成長のための仕組みが見えず、自分がこの先どうなっていけるのか将来に対して不安を感じてしまうことも。
このギャップが放置されると、優秀な人材ほど成長機会を求めて外部に流出するリスクが高まり、組織としての活力や定着率にも影響します。
《ギャップ改善のポイント》
・社内でどのようなキャリアパスが描けるのか、事例やモデルを示して共有する
・成長機会につながる研修、プロジェクト参画、ジョブローテーションなどを整備する
・上司との面談やキャリア面談を定期的に行い、本人の志向や希望を把握する
・「成長が評価につながる仕組み」を構築し、挑戦意欲を高める
・社長や経営層が直接「社員の成長を期待している」というメッセージを発信する
8.「貢献実感」のギャップ

社長や経営層は「社員一人ひとりが組織の成長にしっかりと貢献している」と信じていても、現場の社員には「自分の仕事が会社や社会にどう貢献しているのか」が見えにくくなっていることがあります。
特に組織が大きくなると、業務が細分化されることで自分の役割の意義や成果が全体とどうつながっているのかが分かりづらくなり、「やらされ感」やモチベーション低下につながることもあります。
このギャップが広がると、社員のエンゲージメントが下がり、生産性や定着率にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
《ギャップ改善のポイント》
・自社のミッション・ビジョン・事業の意義を繰り返し発信する
・社員一人ひとりの仕事と組織全体の成果や社会貢献とのつながりを言語化して示す
・定期的に組織全体の成果や進捗を共有し、個人の貢献を認め称賛する
・上司との面談などを通じて「あなたの仕事がどう貢献しているか」を直接フィードバックする
・業務プロセスや成果が他部門・顧客にどう影響しているかが分かるような社内情報共有を工夫する
ギャップ改善に向けた5つの具体的施策
理念やビジョンが正しく浸透し、一人ひとりが自律的に行動できる組織づくりのために。ここでは、よくあるギャップ改善に効果的な「5つの具体的な施策」と、それを支えるツールや仕組み例をご紹介します。
1.半期や年度のはじめに「経営方針発表会」を実施
組織の方向性やビジョンを全社員に共有するためには、半期や年度初めに「経営方針発表会」を行い、社長の想いや今期の方針を直接伝える施策が効果的です。その際、メッセージが正しく、かつ共感をもって伝わるよう、視覚的にもわかりやすい資料の準備が不可欠です。
《必要なツール》
→正しく伝わる「経営方針発表資料」

2.社長メッセージを月1回程度 社内SNSや社内報で発信
理念や方針の浸透には、継続的な情報発信が欠かせません。社長の考えや最新の経営状況を月1回程度、社内SNSや社内報で発信することで、社員との距離感を縮め、日常的にビジョンへの共感を育むことができます。そのためには「思わず読みたくなる」工夫を凝らした社内報づくりが効果的です。
《必要なツール》
→読みたくなる「社内報」
3.管理職研修に「理念・ビジョンを語る力」を育てるワークを導入
理念やビジョンは経営層だけでなく、現場を率いる管理職が自らの言葉で語れることが重要です。管理職研修に「理念・ビジョンを語る力」を育てるワークを組み込み、自分ごと化を促すことで、現場への浸透が進みます。そのためには、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)開発をもとにした、自社ならではの研修資料が有効です。
《必要なツール》
→MVV開発から「独自の研修資料」

4.評価項目に「理念・ビジョンに沿った行動」を加える
理念やビジョンが浸透するためには、評価制度との一貫性が不可欠です。また、社員が「どんな行動が求められているのか」を理解し、行動につなげるには、理念・ビジョンに沿った行動指針を評価項目に組み込むことが効果的です。その実現には、現在の評価制度の見直し・整備が必要になります。
《必要なツール》
→評価制度の刷新・整備

5.現場ワークショップで「理念が業務にどう関係するか」を対話する機会を作る
理念やビジョンが現場レベルで具体的な行動に落とし込まれるためには、社員自身が「自分の業務とどうつながっているのか」を考える対話の場が欠かせません。そのためには、部門ごとにワークショップやキャラバンを実施し、理念の実践例や気づきを共有することで、現場への浸透を促進する取り組みが効果的です。この際に活用できるのが、理念や行動指針をわかりやすくまとめた「クレドブック」です。
《必要なツール》
→キャラバンに活用する「クレドブック」

まとめ:組織拡大によって生じる社員との「8つのギャップ」と「改善策」
いかがでしたでしょうか?組織が成長する過程では、意図せず生まれてしまう“ギャップ”が少なくありません。今回ご紹介した8つのギャップと改善策、そして具体的な施策例を参考に、自社に合った取り組みを進めていただくことで、社員の意欲と組織の一体感をより高めるきっかけになれば幸いです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
《関連するブランディング実績》
Prev
社長依存の組織から社員主導型組織へ






