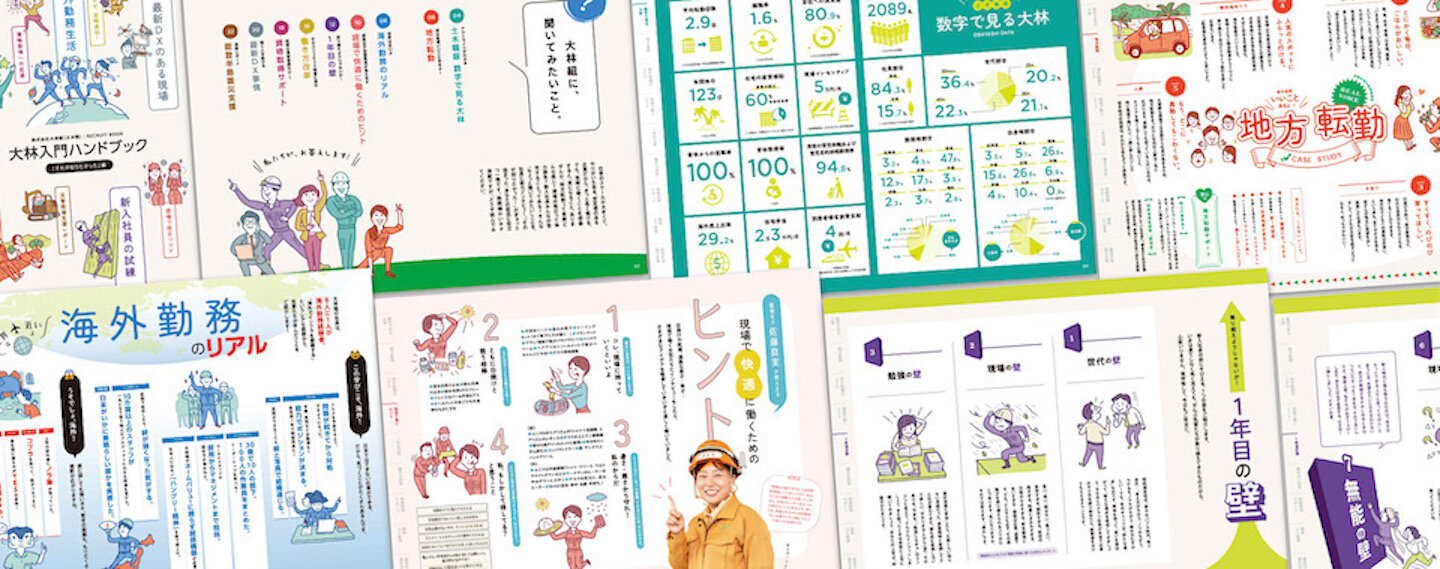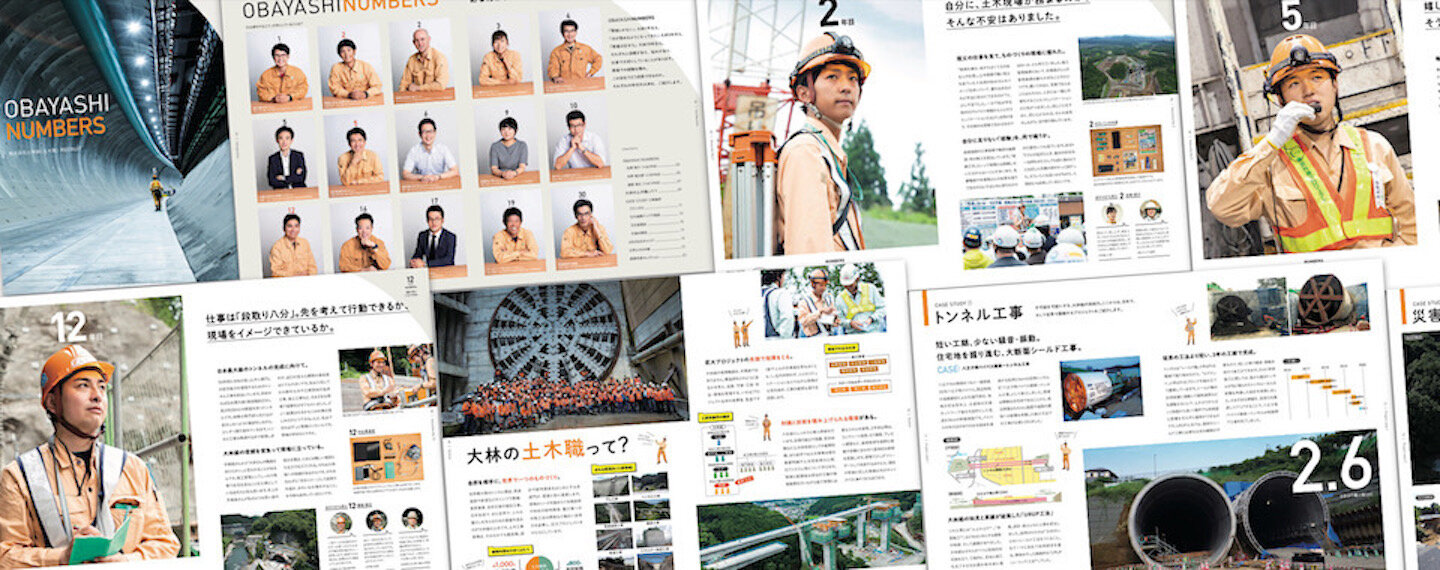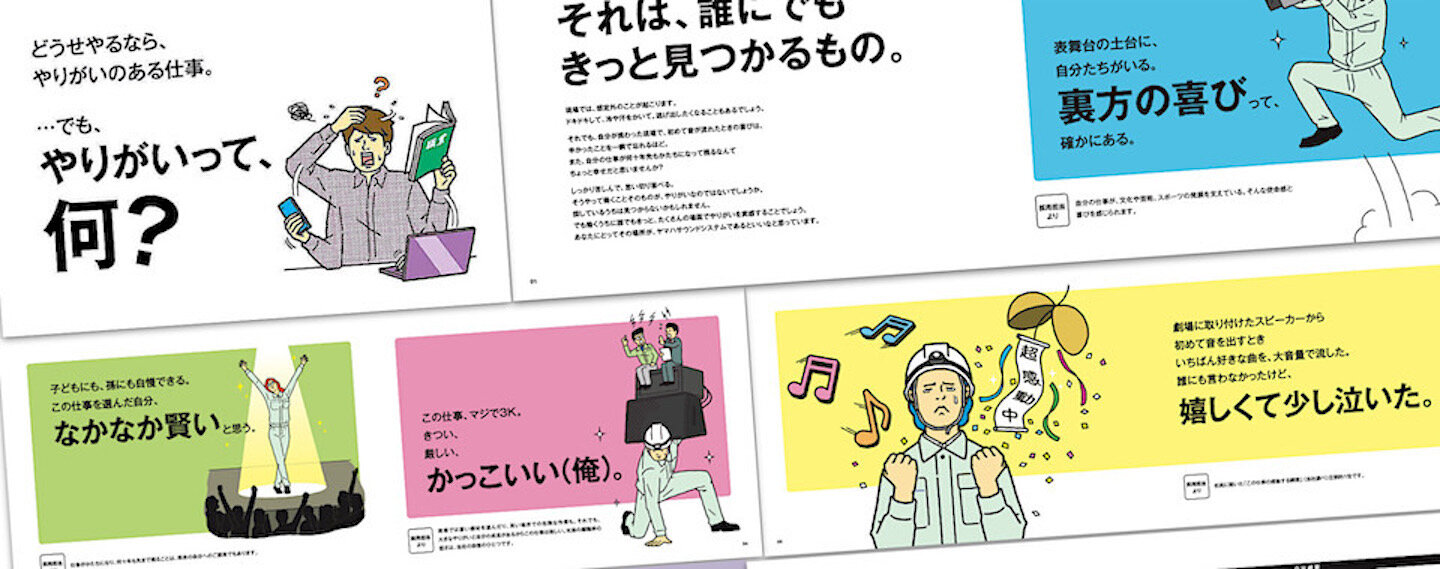219
建設業の採用パンフレット制作を成功へと導く、5つの準備と6つの心構え
「この会社で働きたい」をつくる、採用パンフレット。
求職者に伝わる採用パンフレット作成術を、企画・デザイン・制作のポイントまで分かりやすく紹介します。
採用パンフレットが変える、建設業の採用力
採用パンフレットは、単なる会社案内ではありません。求職者が「この会社で働きたい」と感じるかどうかは、第一印象の設計次第。特に建設業界では、仕事内容が伝わりづらかったり、業界に対する誤解や先入観を持たれていたりすることが多いため、パンフレットという“ビジュアルと言葉”のツールを活用した情報発信が大きな意味を持ちます。
ここでは、建設・建築業に特化した採用パンフレットの作成に必要な視点と流れを、ステップごとにご紹介。経験がなくても安心して取り組めるよう、実際の制作事例を交えながら、効果的なアウトプットへと導きます。
採用パンフレット作成に向けた5つの準備

採用パンフレットを効果的に活用するためには、ただ“かっこよく作る”だけでは不十分です。とくに建設業では、求職者にとって仕事内容や現場のイメージがつきにくく、不安や誤解を抱かれやすい業界でもあります。
だからこそ、事前準備の段階から「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にし、会社の魅力を本質的に届けることが大切です。
以下に、採用パンフレット制作に入る前に押さえておくべき準備ステップをまとめました。
1.採用ターゲットの明確化
どんなに魅力的なデザインやコンテンツであっても、ターゲットが明確に定まっていなければ、企業の魅力や強みは正しく伝わりません。そのため、採用パンフレットの作成では、効果の最大化に向け「誰に向けて作るのか」を明確化することが大切です。自社が本当に採用したい人物像を具体的に描くことで、パンフレットの構成やトーン、伝え方などにブレがなくなります。
《想定する人物像を明確にする》
まず「どんな人に来てほしいか」を明確にすることが重要です。年齢や経験だけでなく、価値観や志望動機まで含めて理想の人物像を具体的に描くことで、伝えるべき内容や言葉選びがはっきりしてきます。
・年齢層:新卒か中途か、20代前半か30代かなど
・経験やスキル:未経験歓迎か、施工管理経験者など専門性が必要か
・価値観や志向性:安定志向か成長志向か、チームで動きたいのか一人で完結したいのか
・志望動機の傾向:「地元で働きたい」「手に職をつけたい」「社会貢献性のある仕事がしたい」 など
《ターゲットが抱えやすい不安や疑問を言語化する》
求職者が応募を迷う背景には、さまざまな不安や誤解があります。以下のような「心の声」を想定し、それに応えるコンテンツを盛り込むと効果的です。
・建設業って体力的にきつそう…
・未経験でも本当にできるの?
・休みや働き方はどうなっているの?
・社内の雰囲気や人間関係はどう?
・女性でも活躍できる?
・将来どんなキャリアが描けるの? など
2.自社の魅力・強みの棚卸し
採用パンフレットで会社の魅力を正しく伝えるためは、まずは自社の“強み”を正確に把握しておくことが大切です。また、求職者が会社や仕事に求めるポイントは、企業側が思っているポイントとは必ずしも一致するとは限らないため、多角的な視点で自社を深掘りしていくことが大切です。
《他社にはない「自社らしさ」を整理する。》
自社ならではの魅力や、他社と差別化できるポイントを具体的に洗い出します。ここで大切なポイントは、必ずしも唯一である必要はないという点です。まずは、何が・どこが自社らしいのかを洗い出しましょう。
・仕事のやりがい:地域に貢献できる/一貫して関われる/感謝の言葉を直接もらえる など
・成長機会:若手でも責任ある仕事を任される/資格取得支援制度がある/キャリアパスが明確 など
・社風・雰囲気:面倒見の良い先輩が多い/上下関係がフラット/仕事と私生活の両立がしやすい など
《現場社員や若手社員へのヒアリング》
経営層や採用担当者の視点だけでは、求職者を置き去りにした一方的なアピールになってしまうことも。それを踏まえ、実際に現場で働く社員、とくに若手社員から「リアルな声」を集めることも大切です。
・入社前と後でギャップはあったか?
・この会社で働いていて良かったと感じる瞬間は?
・実際の仕事内容や1日の流れは?
・社内の雰囲気や人間関係は? など
3.採用ストーリーの構築
採用パンフレットは単なる情報の羅列ではなく、一貫したストーリーとして伝えることで、求職者の心に深くリーチする構成にすることが大切です。またそのストーリーには、企業が「どんな人と、どんな未来を創りたいのか」というメッセージが込められている必要があります。
自社の目指す方向性や価値観と、採用したい人物像とをつなげることで、共感を生む“採用ストーリー”の企画構成が見えてきます。
《求める人物像と描きたい未来を言語化する》
「自社は何のために人を採用するのか?」「どんな人と未来を築きたいのか?」を、企業の成長ビジョンと重ねて明確にします。 “企業としての想い”があると、求職者は「ここでなら自分の力を活かせそう」と未来を重ねることができます。
・地域密着の建設会社として、地元のまちづくりに貢献していきたい
・技術継承を進め、若手が主役になる職場を実現したい
・働く人が誇りを持てるような、風通しの良い組織をつくりたい など
《ミッション・ビジョン・バリューとのつながりを意識する》
企業の掲げる理念(ミッション・ビジョン・バリュー)と採用の方向性に一貫性があることで、メッセージに統一感が生まれ、その積み重ねが求職者との信頼関係構築につながります。単なる一過性のスローガンではなく、それが現場の働き方や人材育成、評価制度などとどう結びついているかを、具体的に伝えるのがポイントです。
・ 「人を大切にする」というミッションが、実際に新人教育やチーム体制にどう反映されているか
・「地域貢献」を掲げる会社が、社員の地域活動参加をどう後押ししているか など
4.掲載内容の構想・構成案作成
採用パンフレットは、「何を・どの順番で・どう伝えるか」がとても重要です。せっかく魅力的な情報を持っていても、構成が整理されていないと読み手には伝わりません。
そのため、制作前の段階で「掲載する内容」と「ページ構成」をしっかりと検討しておくことが、成果につながる採用パンフレットづくりの土台となります。
《必要な情報をリストアップし、目的別に整理する》
パンフレットは限られた紙面(ページ数)となるため、伝える内容に優先順位をつける必要があります。例えば、次のような情報を検討し、それぞれの役割と目的を明確にしましょう。
・会社紹介:企業理念、沿革、事業内容、ビジョンなど
・職種説明:募集職種ごとの仕事内容、必要なスキル、やりがい
・1日の流れ/スケジュール:実際の勤務イメージがわくように可視化
・働く環境や制度紹介:福利厚生、研修制度、キャリアアップの仕組み
・社員インタビュー:若手社員や中堅社員の声、入社の決め手、仕事の魅力
・代表メッセージ:トップからの想いや採用への期待 など
《写真・図解・チャートなど、視覚的要素で理解を促進》
採用パンフレットは、「企業の第一印象」を決めるコミュニケーションツールです。読み手(求職者)は、文字情報だけでなく「ビジュアル」で直感的に企業を印象付けるため、「読みたくなる」「わかりやすい」「共感できる」と感じる一冊を目指し、全体像をしっかり設計していきましょう。
・写真:現場の雰囲気や社員の表情が伝わるものを多用
・図解・チャート:キャリアパスや研修制度、業務フローなどを図式化して見せる
・アイコン・イラスト:情報をやさしく伝えるための工夫として効果的
・見出し・レイアウト設計:視線の流れを意識した紙面構成で、読みやすさを確保
5.制作スケジュールと関係者の確認
採用パンフレットの制作は、多くの工程と複数の関係者が関わるプロジェクトです。取材や撮影、原稿チェックなど、それぞれに時間と準備が必要になるため、全体のスケジュールを事前に設計し、社内の関係者とスムーズに連携できる体制を整えることが大切です。
《主な制作フロー》
まずは、制作にかかる一連の流れを把握し、それぞれに必要な期間を見積もることが大切です。また、制作期間は企画着手から納品まで3ヶ月程度の時間を要するのが一般的なため、採用シーズンや会社説明会など、活用時期から逆算してスケジュールを設計しましょう。
Step01.社内打ち合わせ・要件の確定
→人事担当者:全体管理、コンテンツ内容の調整
Step02.企画・構成の立案・決定
→制作会社:制作パートナーの選定
Step03.デザイン制作・修正
→制作会社:デザイン提案〜修正作業
Step04.社員インタビュー
→現場社員・若手社員:インタビューや撮影に協力
Step05.代表メッセージ
→経営層・代表者:代表挨拶やビジョンの発信
Step06.写真撮影(現場・人物)
→オフィス・現場など撮影日程とカットの調整
Step07.原稿作成・社内チェック
→広報・総務:会社情報やデザイン監修
Step08.最終確認・印刷発注
→制作会社:最終校正〜印刷指示
採用パンフレット制作を成功へと導く6つの心構え

採用パンフレットは、単なる会社案内ではなく、求職者との「対話の入り口」です。特に建設業界では、業界へのイメージや仕事の理解度が低いことから、初対面の印象で入社の気持ちが大きく左右されます。
だからこそ大切なのは、“一方的に伝える”のではなく、求職者の立場に立ち、「知りたいことにちゃんと答える」こと。そして、言葉やデザインに“共感”や“安心”を込め、「ちょっと話を聞いてみたい」と感じてもらえるきっかけをつくることです。
ここでは、採用パンフレット制作を成功に導くための6つの視点をご紹介します。
1.求職者視点で「不安」を払拭する構成を
多くの求職者は、建設業に対して「自分にできるのか」「仕事内容がよく分からない」といった不安を抱えています。その不安にしっかりと応える構成こそが、応募の“ハードル”を下げる第一歩です。
・仕事内容の具体性:「何をする仕事か」が一目で分かる職種説明を
・働くイメージ:「1日の流れ」や「職場の雰囲気」を写真付きで
・仲間の存在:「先輩の声」でリアルな安心感と親近感を演出
一方的な説明ではなく、「不安に寄り添い、答える」という姿勢が伝わる採用パンフレットを目指しましょう。
2.“読み込ませる”より、“引き込む”構成へ
近年の求職者は、隅々まで文字を読み込むというよりも、「パッと見た印象」で直感的にその企業を判断しています。そのため、引き込む工夫=視覚的導線がとても重要です。
・表紙やファーストビューで「なんだか気になる」と思わせる構成
・どのページから見ても魅力が伝わる“散らし読み対応”のレイアウト
・長文ではなく、キャッチコピーや図解で「見てわかる」設計に
「伝える」のではなく「感じてもらう」。そんな視点で、構成全体を考えていくことが大切です。
3. 会社の“らしさ”が伝わる企画・デザインに
どの会社にも、言葉では伝えにくい“空気感”や“人柄”があります。採用パンフレットでは、その雰囲気をビジュアルで直感的に伝えることが重要です。
・社員の表情が見える自然な写真
・フォントやカラーで表現する「安心感」「元気」「誠実さ」
・表紙や見開きで、一目で“会社の温度”が伝わる構成に
読み手が「ここで働く自分」をイメージできるような世界観づくりが、信頼や共感を生むきっかけへとつながります。
4.言葉選びや遊び心で「共感」を
専門用語や硬い表現だけでは、心には届きません。採用パンフレットにおいては、わかりやすさ・親しみやすさ・やさしさが大切です。
・専門用語を避け、シンプルでやさしい表現に
・社員の声や会話をそのまま載せることで「人柄」が伝わる
・クスッと笑えるコピーや、ユーモアのある構成も効果的
「なんかいいな」「話しやすそうな会社だな」と思ってもらえることが、応募の後押しになります。
5.働く姿を“ストーリー”で見せる
単なる「仕事内容の説明」ではなく、働く人のストーリーを見せることで、共感と想像が生まれます。
・入社理由や不安を乗り越えた体験談
・成長して自信を持てるようになったエピソード
・仕事中だけでなく、休憩やイベントなど日常の一コマも掲載
こうした“人物語”を伝えることで、読み手は「自分にもできそう」「自分もその輪に入りたい」と感じられるようになります。
6.こんな声を引き出す採用パンフレットに
最終的に目指したいのは、求職者からこんな声が聞こえてくる採用パンフレットです。
・「思ってたより、建設業って楽しそう!」
・「職人って、かっこいい大人だと思った」
・「ここなら、自分にもできそうな気がする」
・「ちょっと話、聞いてみたいな」
その一言が生まれるかどうかは、採用パンフレットでの“伝え方”次第です。情報を届けるだけでなく、感情を動かす。それが、採用パンフレットに求められる本当の役割です。
建設業界の“魅力”をまっすぐ届ける採用パンフレット5選
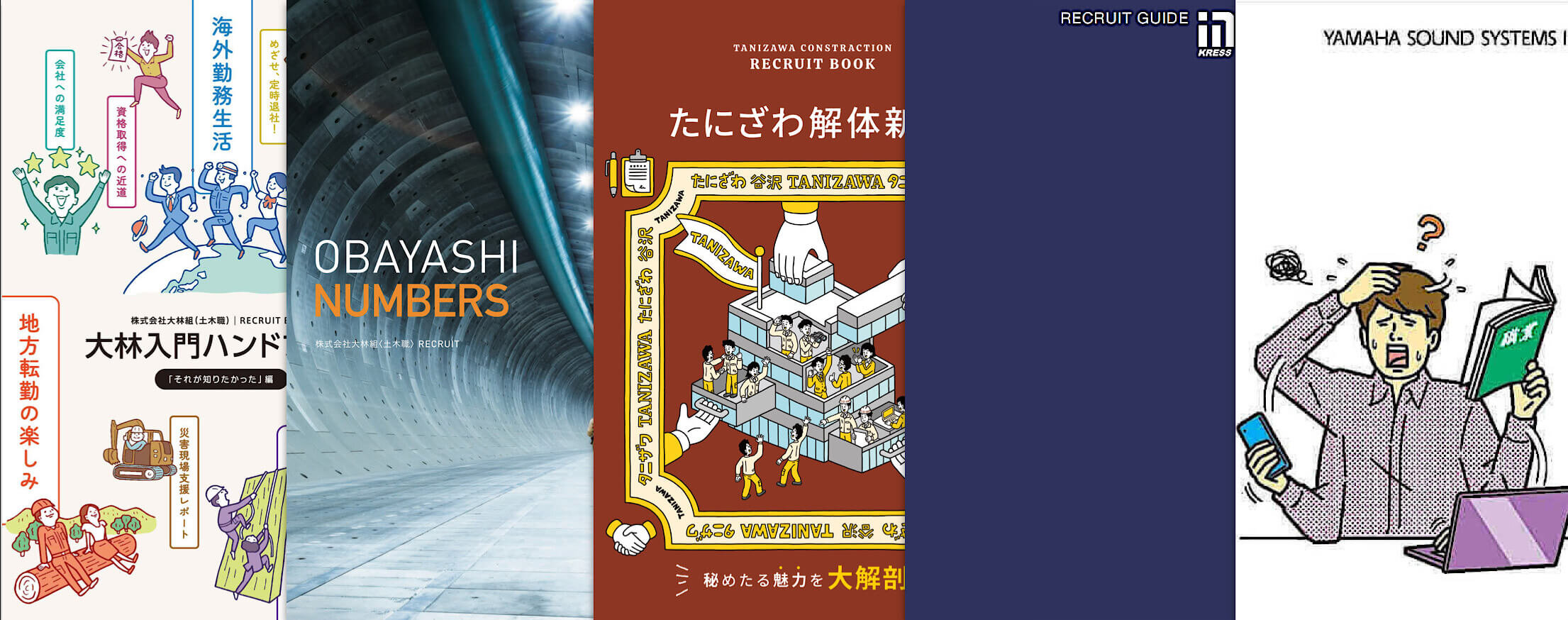
一冊のパンフレットが、未来の出会いを引き寄せる。
学生や求職者が最初に出会う企業の姿。それを形にするのが、採用パンフレットです。たった一冊の中に、会社の魅力や働く人の想いが込められていれば、「ここで働きたい」と思わせるきっかけになる。そんな可能性を秘めています。
ここでは、建設業界における採用パンフレットの優れた実例を5つご紹介。企業が抱える採用課題に真摯に向き合い、「共感」「納得」「期待感」を丁寧に届けるために工夫を凝らした事例ばかりです。
キャラクターを活かして親しみやすさを演出したり、社員のリアルな声で安心感を伝えたり、時には“やりがいと責任”を正直に語ることで誠実さを表現したり、その手法はさまざま。デザインや構成、メッセージの伝え方に企業らしさがあふれるこれらのパンフレットには、“未来の仲間”とつながるためのヒントが詰まっています。
【Works01】学生と本音で向き合う、信頼ベースの採用ハンドブック
「知りたい」にちゃんと答える。それが信頼の第一歩。
建設業界に対する漠然とした不安や疑問。それを放置せず、きちんと受け止め、言葉にして伝える。そんな“まっすぐな採用姿勢”をかたちにしたのが、大林組の採用ハンドブックです。
制作の起点となったのは、若手社員へのヒアリング。就活当時に感じていた不安や「知りたかったけど聞きづらかったこと」を掘り下げ、働き方や女性のキャリア、配属部門の実情、海外転勤のリアルなど、あえて“聞かれにくいこと”にも率直に答える構成にしました。
なかでも印象的なのが、「1年目の壁」に焦点を当てた特集ページ。入社直後に誰もが感じる戸惑いに寄り添い、あたたかいトーンとユーモアのあるイラストで、「大丈夫、ひとりじゃないよ」とそっと背中を押してくれます。
このハンドブックは、見た目の華やかさだけではなく、誠実さと共感を大切にした一冊。学生との信頼関係を築く“入口”として、採用コミュニケーションの本質を体現しています。
【Works02】土木という仕事の本質にふれる、大林組〈土木職〉採用パンフレット
スケールの大きな現場で、人が育つ。
ダイナミックなインフラ整備の最前線。そこにあるのは、最先端の技術だけでなく、ひとつひとつの判断や工夫に責任を持つ“人”の仕事です。大林組が制作した〈土木職専門〉採用パンフレットは、そんな土木の仕事の魅力と奥深さを、リアルに伝えることを目的とした一冊です。
軸となるのは、働く人のリアルなキャリアと成長の軌跡。キーワードは「OBAYASHI NUMBERS」。入社年次の異なる社員たちが、それぞれの視点から仕事のやりがいや挑戦を語り、成長のプロセスを“数字”とともに見える化。プロジェクトの裏にあるチームワークや人材の多様性も浮かび上がります。
さらに、土木の知識がなくても直感的に“すごい”と感じられるよう、圧巻の現場を切り取った写真集ページも掲載。静かな迫力と美しさで、土木職の世界に引き込まれる構成になっています。加えて、パンフレットと連動した採用動画も制作し、印象に残る体験価値を設計しています。
大きな構造物をつくるのは、人の積み重ねた努力と技術。このパンフレットは、そのリアルな姿を未来の仲間に届ける、キャリアと誇りを伝える採用ツールです。
【Works03】たにざわ解体新書 採用パンフレット
「こんな会社だったんだ!」その発見が、未来の出会いにつながる。
入社して初めて「実はすごく良い会社だった」と気づく。そんな声が多かった谷沢建設。
もし、その魅力、もっと早く知ってもらえたら? そんな想いから誕生したのが、採用パンフレット「たにざわ解体新書」です。
大手と比べて知名度では不利。でも、“中身”で勝負できる企業には、確かな強みがあります。私たちはその魅力をわかりやすく届けるために、あえてユニークなネーミングと、親しみやすいビジュアル・言葉づかいを採用。イラストや軽快なコピーを散りばめながら、会社の価値観や職場の空気感までしっかり伝える一冊に仕上げました。
取り上げたのは、仕事内容だけではありません。社員の人柄や働き方、チームの雰囲気など、「ここで働く自分」をイメージできる“リアルな判断材料”にフォーカス。見た人が「ちょっと面白そう」「会って話してみたい」と感じるような、温度のある構成を心がけました。
知名度に頼らず、等身大の魅力で勝負する。「たにざわ解体新書」は、そんな採用のあり方を体現した一冊です。
【Works04】向いてる人・求めている人材。採用パンフレット
“自分に合う仕事”を見つけるために、あえて本音で伝える。
就職活動で本当に大切なのは、「自分に向いているかどうか」。だから鹿島クレスは、耳ざわりのいい言葉を並べるのではなく、あえて“向いている人・向いていない人”という切り口から、仕事のリアルを伝える採用パンフレットを制作しました。
建設現場を支える技術者には、冷静な判断力や周囲との調整力、そしてチームを動かすバランス感覚が欠かせません。その前提のもと、「○○な人は向いている」「××な人は難しい」といった本音ベースのメッセージを見開きで対比させ、求める人物像を明確に表現しました。
後半では、実際のプロジェクト現場の写真や社員の声を掲載。先輩社員と新入社員の対談形式で、仕事のやりがい、悩み、成長エピソードをリアルに紹介しています。「この人も最初は不安だったんだ」「自分にもできるかもしれない」。そんな気づきを促す構成で、仕事選びに対する納得感を高めています。
誰かにとっては最高の職場でも、自分にとってそうとは限らない。だからこそ、正直に、具体的に伝えることが大切だと鹿島クレスは考えます。
このパンフレットは、将来を真剣に考えるすべての人へ向けた、“自分らしく選ぶ”ための一冊です。
【Works5】やりがいって、何?|採用パンフレット
見えないけれど、確かに響く。音の裏側にあるプロの誇り
スポットライトの当たらない場所にこそ、本物の仕事がある。ヤマハサウンドシステムの採用パンフレットは、そんな“音の裏方”としての誇りとやりがいを、やさしい言葉とあたたかなイラストで丁寧に伝える一冊です。
舞台やホールの音響設備を提案・設計・施工するという仕事は、決して派手ではありません。目立たず、知られることも少ないかもしれない。けれど、音が響いたその瞬間、「自分の仕事が空間を完成させた」という確かな手応えがある。その実感を、読者にそっと届けます。
コンセプトは「やりがいって、何?」。
仕事の舞台裏をあえてコミカルに描きながらも、そこにあるチームの連携や、空気をつくる責任感、そして音で空間を彩る達成感など、静かで力強い“仕事の深み”を感じられる構成になっています。
経験や知識はなくても大丈夫。このパンフレットには、「音を支える仕事って、こんなに面白いんだ」と思ってもらうための、まっすぐな想いが込められています。音の世界の裏側に挑む、未来の仲間に向けた等身大のラブレターです。
まとめ:建設業の採用パンフレット制作を成功に導く、5つの準備と6つの心構え
採用パンフレットは、企業の魅力や想いを届ける“第一印象の設計図”です。本記事では、建設業に特化した採用パンフレットづくりのために、「5つの準備」と「6つの心構え」、そして共感を生む実例5選をご紹介しました。採用パンフレット制作の取り組みが、貴社と未来の仲間をつなぐきっかけとなれば幸いです。
ブランディングチーム
パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。
記事制作/プロデューサー
ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。
Producer
CEO 豊田 善治
東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。